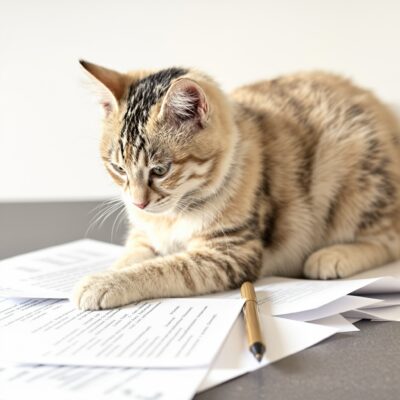
愛猫が病気やケガをしたとき、治療費が高額になることは珍しくありません。とくに猫は腎臓病や尿路結石など慢性的な病気にかかりやすく、長期的な通院や手術が必要になるケースもあります。ペット保険に加入していれば治療費の一部を保険金でカバーできるため、経済的な負担を大幅に軽減できます。
例えば猫の腎不全治療では入院や継続的な投薬が必要になり、数十万円規模の費用がかかることもあります。ペット保険があれば高額な手術費や入院費にも備えることができ、「費用が心配でベストな治療を諦める」といった事態を防げるのです。また、不慮の事故による骨折や誤飲による緊急手術など、突然のトラブルにも保険がお守りとなってくれます。
獣医師としても、万が一に備えての保険加入は若いうちから検討する価値があると感じます。実際、「若いから大丈夫」と保険未加入だった猫が突然大病を患い、高額治療に直面して飼い主さんが悩まれるケースを目にしてきました。元気なうちに備えておくことで、いざというときに迅速に治療を受けさせてあげられるでしょう。
猫のペット保険を選ぶポイント
猫の保険を選ぶ際は、補償内容や保険料をしっかり比較検討しましょう。以下に選び方の重要ポイントをまとめます。
- 補償範囲の広さ: 病気やケガの幅広い補償があるか確認します。特に歯周病や慢性疾患までカバーされている保険がおすすめです。歯のトラブルは全身状態に影響することもあり、治療には全身麻酔や手術が必要になる場合もあります。しかし保険商品によっては歯科治療が補償対象外のものもあるため注意しましょう。また、猫に多い腎臓病や膀胱炎、異物誤飲といったケースも補償されるかチェックが必要です。
- 補償額・回数と限度: 保険ごとに年間いくらまで支払われるか(年間補償限度額)や、1回の手術あたりの限度額、通院・入院の補償日数や日額が定められています。理想は手術や入院の補償が無制限のプランですが、現実には上限がある商品も多いです。ただし手術補償は年間2回以上対応しているもの、入院・通院補償の日額や日数制限がゆるやかなものを選ぶと安心でしょう。入院や手術が長引いた場合でも、限度が高い(あるいは無制限の)保険なら自己負担を大幅に減らせます。
- 補償割合と自己負担: ペット保険では治療費の何割を保険金で補償するか(補償割合)を50%、70%、100%などから選べます。一般的に補償割合が高いほど自己負担は少なくなりますが、その分保険料は高めになります。おすすめは70%前後のプランです。自己負担30%なら高額治療でも負担を抑えつつ、保険料とのバランスも良好です。また免責金額(自己負担の最低額)がない商品を選びましょう。免責があると少額の治療費は補償されず負担増になるため、免責0円の保険が安心です。
- 通院補償の有無: プランによっては通院を補償しない「入院・手術限定」のタイプもあります。**若い猫(0~6歳程度)**であれば通院補償なしプランで保険料を節約する選択肢もあります。軽い風邪や下痢程度なら保険を使わずとも賄える場合、高額になりやすい入院・手術だけ備える手頃なプランは魅力です。ただし高齢になるにつれて通院頻度も上がるため、シニア期に差し掛かったら通院補償ありのプランへ切り替えることも検討しましょう。
- 加入条件と継続年齢: 終身まで更新可能か、新規加入できる年齢制限は何歳までかも重要です。例えば加入可能年齢が上限7歳までの保険だと、8歳以降に保険に入りたくても加入できなくなります。幸い主要な保険会社の多くは終身継続可能(一度入れば一生更新可)ですが、新規加入年齢には制限があります。愛猫がシニアになる前に加入しておくことが大切です。また既往症がある場合、告知によっては補償対象外の特約付きで加入できる会社(後述のPS保険など)もあります。
- 保険料の負担: 家計に無理なく支払える保険料かどうかも現実的なポイントです。補償内容が手厚くなるほど保険料は上がりますが、各社で同じ70%補償プランでも保険料には差があります。また、年齢とともに保険料が値上がりする商品が大半です。できるだけ保険料の上昇が緩やかで、トータルで支払う保険料が安い商品を選ぶと良いでしょう。後述するおすすめ保険の中では、保険料が全年齢で一定のプラン(例:アイペットは9歳以降値上がりなし)や、シニアでも比較的割安に設定されている会社もあります。
- 付帯サービスや特約: 保険によっては24時間相談できる獣医師ホットライン、ペット賠償責任特約(他人や他の動物にケガをさせた際の補償)などのサービスが付いているものもあります。特約は必要に応じて付加できますが、その分保険料も上乗せになるため自分に必要なサービスか見極めましょう。また多頭割引など割引制度がある場合、複数のペットを飼っているご家庭ではお得に加入できます(例:アイペットやアニコムは2頭以上で保険料割引あり)。
獣医師アドバイス🚑:「なるべく若いうちに保険加入を!」
ペット保険は健康状態が良好なうちに加入するのがポイントです。高齢になって病気が見つかってからでは新規加入が難しかったり、病気部分が補償対象外になることも。元気なうちに備えておくことで、後から「入っておけば良かった…」と後悔せずに済みますよ。
【2025年最新】猫のペット保険おすすめ人気5選
それでは、上記の選び方ポイントも踏まえて2025年時点でおすすめできる猫向けペット保険5選を、ランキング形式で紹介します。保険料の目安や補償内容、特徴を比較し、ご自分の愛猫に合ったプラン選びの参考にしてください。
まずは今回紹介する5つの保険の主なスペックを簡単にまとめました。
猫のペット保険おすすめ5選比較表
| 順位 | 保険会社・プラン名 | オススメ度 | 補償割合 | 年間補償上限額 | 月額保険料* | 窓口精算 | 新規加入年齢 | 主な特徴・メリット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PS保険(ペットメディカルサポート) | ★★★★★ | 70% | 110万円 | 約2,000円 | ✗ | 制限なし | 業界最安級の保険料で幅広い補償。歯科治療も対象。持病がある猫でも特約付きで加入可能 |
| 2位 | アイペット損保「うちの子」 | ★★★★☆ | 70% | 122.4万円 | 約3,000円 | ✓ | 12歳11ヶ月まで | 補償額トップクラス。窓口精算対応で利便性抜群。9歳以降保険料一定 |
| 3位 | FPC「ペットほけんマックス」 | ★★★★☆ | 70% | 180万円 | 約1,300円 | ✗ | 制限なし | 高額補償と低価格を両立。通院無制限。各分類60万円まで回数制限なし |
| 4位 | アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」 | ★★★☆☆ | 70% | 84万円 | 約3,300円 | ✓ | 7歳まで | 老舗の安心感。提携病院数No.1(6,800件以上)。予防サービス充実 |
| 5位 | SBIペット保険「プラン70スタンダード」 | ★★★☆☆ | 70% | 70万円 | 約1,500円 | ✗ | 11歳11ヶ月まで | 非常に割安な保険料。終身継続可能。基本補償をしっかりカバー |
*月額保険料は0歳の猫・補償割合70%プランの場合の目安(2025年現在)
各保険の適用シーン
| プラン | こんな飼い主さんにおすすめ | 注意点 |
|---|---|---|
| PS保険 | コスパ重視、幅広い補償を求める、多頭飼い、持病のある猫 | 窓口精算非対応 |
| アイペット「うちの子」 | 手厚い補償重視、窓口精算の利便性を求める、シニア猫 | 保険料がやや高め |
| FPC | 高補償と低価格の両立を求める、通院頻度が高い猫 | 窓口精算非対応 |
| アニコム | 初心者、充実したサポート重視、全国どこでも使いたい | 補償上限がやや低め、7歳までの加入制限 |
| SBI | 保険料最重視、基本的な備えで十分、高齢猫の新規加入 | 補償上限が最も低い |
1. ペットメディカルサポート「PS保険」 – 幅広い補償と業界最安級の保険料が魅力
特徴: ペットメディカルサポート株式会社の「PS保険」は、保険料の安さと補償範囲の広さを両立した人気No.1保険です。年間補償上限は110万円と十分で、通院・入院・手術すべて免責金額なしでカバー。歯周病による処置費用や胃腸炎・下痢・嘔吐、膀胱炎・尿石症など他社では補償外になりやすい疾患も対象になります。また業界でも珍しく、現在治療中の持病があってもその疾病を補償対象外とする特約(特定疾病不担保特約)を付けることで加入できる可能性があります。保険金の請求や各種手続きもインターネットで完結でき、利便性も◎です。
おすすめ理由(獣医師の視点): 私も獣医師として、PS保険のコストパフォーマンスの良さには注目しています。他社と比べても全年齢で保険料が割安な傾向があり、かつ高齢になってからの保険料上昇も緩やかなので長期加入による負担が少ないです。それでいて補償内容は充実しており、特に歯の疾患までカバーされているのは大きな安心材料です(歯周病は高齢猫で頻発します)。**「手頃な掛け金でしっかり備えたい」**飼い主さんにとってベストな選択肢でしょう。
適しているケース: 幅広いリスクに万全に備えたい全ての猫ちゃんに向いています。とくに、若い頃から加入して終身まで総合的な補償を受けたい場合に最適です。保険料が抑えめなので多頭飼いで出費を抑えたい方や、シニアまで長く続けやすい保険を探している方にもおすすめできます。また現在治療中の持病があって他社で断られた猫でも、PS保険なら特約を付けて入れる可能性があるため、加入をあきらめていた飼い主さんにも門戸が広い保険です。
申込方法・購入先: 公式サイトからのWEB申込みがおすすめです。資料請求も可能ですが、インターネット割引が適用される場合があるためオンラインでの見積もり・加入が手早くお得です。申し込みから保険金請求まですべてWEB上で完結できるため、忙しい方にも便利です。
2. アイペット損保「うちの子」 – 窓口精算対応&高い補償額で安心
特徴: アイペット損害保険の「うちの子」は、猫の保険契約数で3年連続No.1(2022~2024年調査)を誇る定番人気の総合保険です【※調査概要: 対象商品うちの子/ライト、Tリサーチによる】。年間補償上限は122.4万円と業界トップクラスの手厚さで、通院・入院・手術のすべてに支払限度額が高く設定されています(通院1日上限1.2万円×22日など)。補償範囲も広く、猫で特に多い慢性腎臓病や下部尿路疾患、誤飲事故などもしっかりカバー。最大の特徴は「窓口精算」に対応している点で、対応動物病院であれば治療費の自己負担分のみ支払えばOK、その場で保険精算が完了します。さらに12歳11か月まで新規加入可能で、9歳以降は保険料が上がらず一定になるユニークな仕組みも安心感があります。
おすすめ理由(獣医師の視点): 「うちの子」は補償額・内容ともに非常に充実しており、高額治療への備えとして盤石です。私の患者さんでもアイペットに加入している方は多く、窓口精算のおかげで治療費立替の負担がないと好評です。急な手術や入院でも122万円まで補償されるため、大抵のケースはカバーできます。また高齢猫でも加入しやすい(加入上限年齢が12歳11ヶ月)点や、シニア期の保険料が定額になる点も継続利用に向いています。総合的に見て**「多少保険料が高めでも、手厚い補償と便利さを重視したい」**という方におすすめできます。
適しているケース: 愛猫に万全な医療を受けさせたい飼い主さんに適した保険です。治療費の立替が不要になる窓口清算は、まとまった費用を準備する必要がないため金銭面で不安な方にも心強いでしょう。特に持病のリスクが高まるシニア猫を飼っている方や、通院頻度の高い猫(腎臓病など慢性疾患を抱える猫)には、通院補償が充実した「うちの子」がフィットします。また高齢で他社加入が難しい10歳以上の猫でも12歳までなら新規加入可能なので、シニアから保険検討する場合にも候補になります。
申込方法・購入先: 公式サイトまたは各種ペット保険取り扱い代理店から申し込みできます。アイペットは契約者専用のWebポータルやスマホアプリも整備されており、保険金請求や更新手続きもオンラインで可能です。対応病院であれば保険証を提示して窓口精算できるので、加入後は保険証カードを携帯しておくと良いでしょう。
3. FPC「ペットほけんマックス」 – 高額補償と低価格を両立したバランス優秀プラン
特徴: エフ・ピー・シー株式会社(FPC)の「ペットほけんマックス」は、業界トップクラスの補償額と業界最安級の保険料を両立したコストパフォーマンス抜群の保険です。年間補償上限は合計180万円(通院・入院・手術それぞれ年間60万円までの補償)の高額設定で、各項目の1日あたり・1回あたりの支払い限度は実質無制限(※各項目60万円の範囲内なら回数制限なし)という手厚さです。例えば通院でも日数制限なく支払いを受けられるため、慢性疾患で通院が頻繁な場合にも安心です。それでいて保険料は非常に割安で、子猫0歳時なら月額1,000円台前半から加入できます。補償割合も50%、70%、90%から選択可能で、自分に合ったプラン設定が可能です。
おすすめ理由(獣医師の視点): FPCの保険は**「高補償=高保険料」という常識を覆すような存在です。私が見る限り、通院・入院・手術トータルの補償額180万円はトップクラスで、実際に支払い実績でも十分な額といえます(よほどの高度治療でなければ年間180万円を超えるケースは稀です)。それを月々約1,200〜1,500円程度で提供できているのは驚きです。ペット保険選びで迷う方に「補償もしっかり、でも保険料は安いものが良い」と相談されたら、真っ先に候補に挙げたい商品です。また支払い限度が明快**(各分類60万円までで何度でもOK)なので、細かな条件を気にせず請求しやすいのも利点でしょう。
適しているケース: 保険料をできるだけ抑えつつ、広範囲な補償を確保したい方にピッタリです。特に若い猫からシニアまで長く続けたい場合、総額の負担が軽く済む点で家計に優しいです。通院無制限なので、持病で通院頻度が高い猫や、今後慢性疾患が心配な猫にも心強いです。ただしFPCは窓口精算非対応のため、一旦全額立替が必要です。貯蓄とのバランスを考え、**「とりあえず高額医療の備えはしておきたいが予算は抑えたい」**という単頭飼いの方から、多頭飼育で1頭あたりの保険料を節約したいご家庭まで幅広くおすすめできます。
申込方法・購入先: 公式WEBサイトや資料請求から申し込み可能です。インターネットからの契約も簡単で、FPC公式サイトではペットの年齢を入力して保険料試算もできます。支払い方法はクレジットカードまたは口座振替に対応しており、月払い・年払いを選択できます。
4. アニコム損保「どうぶつ健保ふぁみりぃ」 – 動物病院ネットワーク充実の老舗保険
特徴: アニコム損害保険の「どうぶつ健保ふぁみりぃ」は、日本で最も歴史のあるペット保険会社による定番の総合プランです。通院・入院・手術を幅広くカバーし、年間補償上限は84万円(補償割合70%の場合)。他社に比べ上限額はやや低めですが、その分使い勝手の良いサービスが揃っています。特筆すべきは提携動物病院の多さで、全国約6,800件以上の動物病院で「窓口清算」(アニコムの保険証を提示して自己負担分のみ支払い)が可能です。これは業界No.1のネットワークで、どこに住んでいても利用しやすい安心感があります。また、アニコムは予防寄りのサービス(健康相談やしつけ相談、季節ごとの健康情報提供など)も充実しており、単なる保険金支払いに留まらない総合サポートが受けられます。なお新規加入は7歳までですが、8歳以上から加入できる「どうぶつ健保しにあ(入院・手術限定)」プランも用意されています。
おすすめ理由(獣医師の視点): アニコムは私たち獣医師側にも認知度が高く、保険対応の手続きもスムーズな印象です。実際に保険証を提示されればその場で自己負担分だけ受け取れば良いので、飼い主さんにとっても医療機関にとっても楽です。補償額の上限(84万円)は他社のトッププランより低めですが、多くの一般的な治療はカバーできる額ですし、「万一足りない場合は貯蓄で補う」という考えで保険料負担を抑えたい方にはバランスが取れています。アニコムのデータ蓄積や分析力も魅力で、例えば同社発行の冊子やアプリでペットの健康傾向や予防法が学べる点も、獣医師監修情報として信頼できます。「保険+アルファのサービスにも価値を感じる」方にぜひおすすめしたいです。
適しているケース: 初めてペット保険に入る飼い主さんや、手厚いサポート体制を求める方に適しています。アニコムは知名度が高く、提携病院も多いため迷ったらとりあえず選んでおいて安心な保険とも言えます。特に通院機会が多くなりがちな子猫の頃からシニアまでトータルにサポートを受けたい場合にフィットします。また、万一7歳までに加入しそびれてしまっても8歳から入れる「しにあ」プランがあるため、高齢猫を迎えた方にも門戸が開かれています。ただし補償上限額をもっと増やしたい方や、保険料を最安に抑えたい方は他プランも検討すると良いでしょう。
申込方法・購入先: アニコム公式サイトや提携ペットショップ・動物病院から申し込みできます。公式サイトでは資料請求やオンライン見積もりが可能です。また、一部の動物病院やペットショップではアニコムの保険加入手続きを代行してくれる場合もあります。契約後は毎年送られてくる「どうぶつ健康保険証」を使って、対応病院で窓口精算が可能です。
5. SBIいきいき少短「ペット保険プラン70スタンダード」 – 手頃な保険料で基本をしっかりカバー
特徴: SBIいきいき少額短期保険(通称SBIペット少短)の「プラン70スタンダード」は、月々の保険料が非常にリーズナブルなフルカバー型保険です。年間補償上限は70万円(補償割合70%の場合)で、通院・入院・手術すべての治療費用を対象とします。特徴は通院・入院・手術それぞれの1日/1回あたりの制限がなく、年間支払限度額内(70万円)であれば何回でも請求可能な点です。保険料は0歳猫で月額1,500円前後と割安で、しかも11歳11ヶ月まで新規加入可能と高齢まで受け入れています。更新も以降終身まで可能なので、途中で打ち切られる心配が少ないです。ただし、窓口精算には非対応のため都度の立替払いと後日の請求が必要です。
おすすめ理由(獣医師の視点): SBIペット保険はその手頃な価格設定から、気軽に加入しやすい点が魅力です。補償上限の70万円はトッププランと比較すると少なめですが、高額治療が必要になる確率はそう高くないという考えのもと、最低限の備えを持っておきたい方に向いています。実際「とりあえず保険に入っておきたいけど高いプランは負担…」という飼い主さんには、SBIのプランは必要十分な補償と割安な掛け金で最適解になるでしょう。終身継続可能なので、若いうちから入り途中で解約せずコツコツ備えていきたいご家庭にも安心です。SBIグループというブランドの信頼感もあり、初めての保険でも敷居が低いですね。
適しているケース: できるだけ保険料負担を抑えたいが基本的な補償は押さえておきたい方にマッチします。例えば完全室内飼いでリスクは低めだけれど万一に備えたい場合や、他の出費が多く家計的に保険にあまり割けない場合でも、このプランなら無理なく継続できるでしょう。また、成猫・高齢猫の新規加入先を探している方にも有力です(11歳までOK)。一方で、がん治療や高度医療までフルに備えたい場合は年間70万円だと不足するケースも考えられるため、カバー範囲より保険料優先の方向けと言えます。複数の猫にまとめて入る際の総額を抑えたい時にも検討すると良いでしょう。
申込方法・購入先: 公式サイトもしくは電話で申し込みできます。ネットから24時間申し込み可能で、契約もスムーズです。保険金の請求は、治療後に必要書類(請求書や明細)を郵送して行います(WEB請求非対応)。手続きはオーソドックスですが、そのぶん保険料の低さにつながっていると言えます。
まとめ:愛猫に合った保険で安心を備えよう
ペット保険は決して安い買い物ではありませんが、「もしもの時の安心料」と考えると心強いものです。特に猫は体調不良を隠しがちで、気づいたときには治療が長期化・高額化することもあります。
今回ご紹介したように、各社ごとに保険料や補償内容、サービスに特徴がありますので、愛猫の年齢・健康状態や飼い主さんの重視したいポイントに合致するプランを選んでみてください。
大切なのは加入して終わりではなく、定期的に見直しつつ賢く活用することです。保険証をお守り代わりに通院時に持参したり、調子が悪いときには遠慮なく保険の24時間相談窓口を利用したりして、愛猫の健康管理にぜひ役立ててください。
ペット保険を上手に活用し、万全の準備で愛猫との毎日を安心して過ごしましょう。万一の高額医療にも備えがあれば、飼い主さんも心にゆとりを持って愛情たっぷりにケアしてあげられますね。
