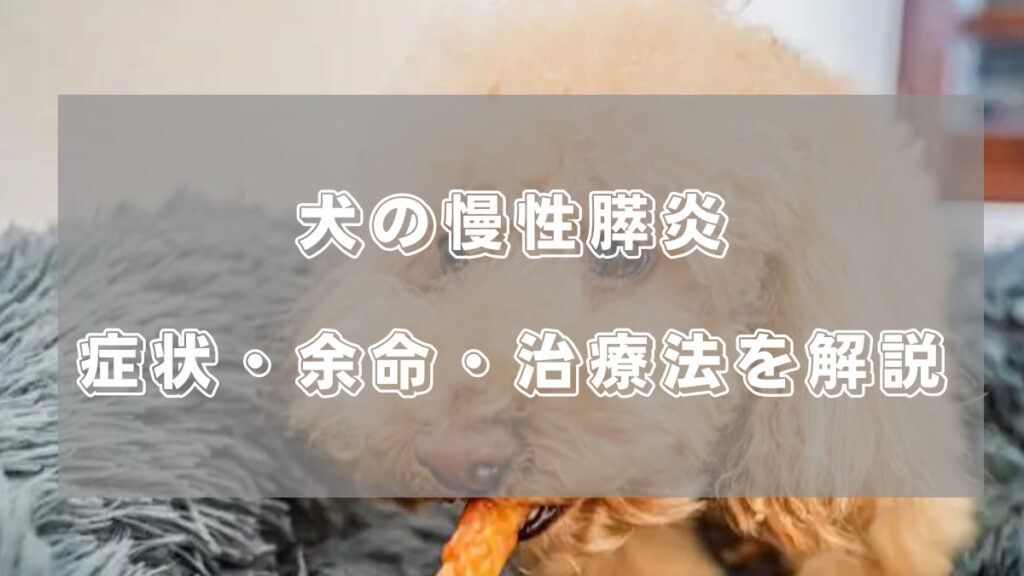
愛犬がときどき嘔吐したり、大好きなおやつを突然食べなくなったり、食後におならや下痢をすることはありませんか? こうした症状に心当たりがある場合、診断が難しいとされる「慢性膵炎」を発症している可能性があります。膵炎という病名自体は聞いたことがある飼い主さんも多いでしょう。しかし、実は膵炎には急性膵炎と慢性膵炎の2種類があり、症状や経過に大きな違いがあります。
急性膵炎は適切な集中治療を行えば1~2週間程度で完治することもありますが、慢性膵炎は残念ながら完治が難しく一生付き合っていく必要がある病気です。慢性膵炎は他の消化器疾患と症状が似ており区別が難しいため、見逃されて発見が遅れがちです。また慢性膵炎そのものは急性のように突然命にかかわることは少ないものの、糖尿病や膵外分泌不全、さらには腎不全など様々な合併症を引き起こしうるため注意が必要です。
本記事では、あまり知られていない「犬の慢性膵炎」について、寿命への影響、主な症状、治療法、適切な食事管理などを現役の獣医師がエビデンスに基づいて詳しく解説します。慢性膵炎の愛犬と暮らす飼い主さんが知っておくべきポイントを網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
膵臓ってどんな臓器?
膵臓(すいぞう)は、犬の胃の下部(幽門付近)から小腸(十二指腸)の起始部にかけて付着している細長いピンク色の消化器官です。膵臓には大きく分けて外分泌機能と内分泌機能という2つの働きがあります。外分泌機能とは、食物の消化を助ける消化酵素(アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなど)を膵臓から分泌し、腸に送る働きです。これらの酵素によって、食べ物中のデンプンや脂肪、タンパク質が小さな分子に分解されます。一方、内分泌機能とはインスリンやグルカゴンといったホルモンを膵臓のランゲルハンス島から分泌し、血糖値を調節する働きです。インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血糖値を上げる作用があり、膵臓はこのように体の消化と代謝の両面で重要な役割を担っています。
膵炎ってどんな病気?
膵炎(すいえん)とは膵臓が炎症を起こしている状態をいいます。膵炎が起こる原因は、膵臓から分泌される消化酵素が正常に働かずに自己消化を起こしてしまうことです。通常、膵臓は自らを守るため消化酵素が膵臓自身を傷つけないしくみを持っています。しかし何らかのきっかけで膵臓の組織がダメージを受けると、酵素が膵臓内で活性化して周囲の組織を消化してしまい、膵臓に炎症が発生します。例えば高脂肪食を一度に大量に食べた場合、膵臓から多量の消化酵素が分泌されます。その消化酵素が膵臓内で過剰に活性化すると膵臓組織を自己消化して炎症を起こし、これが急性膵炎です。
そして慢性膵炎は、この膵炎(多くは急性膵炎)が繰り返し起こることで徐々に膵臓組織が破壊・線維化(瘢痕化)し、膵臓が委縮して機能が低下してしまう進行性の病気です。一度壊れた膵組織は不可逆的(元に戻らない)な変化を遂げます。そのため、慢性膵炎では治療を行っても正常な膵臓組織には戻らず、機能低下が少しずつ進行してしまいます。急性膵炎を繰り返すことで慢性膵炎になるケースが多いですが、逆に慢性膵炎を患っている犬が何かの拍子に急性増悪(急性膵炎の発症)することもあります。慢性膵炎が進行して膵臓の実質細胞が大きく失われると、膵外分泌不全(EPI)(消化酵素の分泌不足による消化吸収不良)や糖尿病(インスリン分泌低下による慢性高血糖)といった疾患を併発することがあります。
このように慢性膵炎は膵臓自体の炎症・機能低下だけでなく、全身の代謝にも影響を与えうる病気です。
慢性膵炎で起こる主な6つの症状
急性膵炎の場合は突然の激しい嘔吐や激痛を伴うことが多いのに対し、慢性膵炎では数ヶ月~数年にわたって断続的に症状が現れる傾向があります。以下のような症状が長期間にわたり繰り返し見られないか、日頃から愛犬の様子を観察してみてください。
- 元気消失・食欲不振: なんとなく元気がなく、食べる量が減ったり好きな物も残す
- 大腸炎症状: 粘液や鮮血が混じる軟便・下痢(大腸性下痢)
- 嘔吐: 時折もどす、昔より嘔吐の頻度が増えた
- 下痢: 水様性の下痢や軟便が続く
- 腹部の不快感や疼痛: お腹を触ると嫌がる、丸くなって痛がる素振りを見せる
- 腹鳴: お腹がゴロゴロと頻繁に鳴る
上記のうち複数の症状が当てはまる場合は、慢性膵炎を発症している可能性があります。慢性膵炎の症状は軽度で非特異的なことが多く(他の病気でもよく見られる症状)、場合によっては無症状のことさえあります。そのため飼い主さんが見逃してしまい、膵炎以外の慢性消化器疾患(腸炎や胃炎など)だと思って経過を見てしまうケースも少なくありません。特に症状が断続的に出たり消えたりを繰り返すため、「少し様子を見よう」と思っているうちに長期化してしまうこともあります。
しかし慢性膵炎がさらに進行すると、嘔吐や下痢による脱水や体重減少、黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)、発熱あるいは低体温、重度の腹痛などの症状が現れることもあります。これらの症状が強く出ている場合には膵臓の炎症がかなり進んでいる可能性があります。また慢性膵炎では、前述のように糖尿病や膵外分泌不全を併発すると多飲多尿、止まらない下痢、脂肪便(脂っぽい便)や重度の体重減少といった症状が出ることがあります。慢性膵炎の症状自体は急性膵炎ほど劇的ではなく緩やかな消化器症状ですが、長期にわたる炎症は着実に膵臓を傷害し合併症リスクを高めます。したがって「最近なんとなく体調が良くない状態が続いている」「年齢のせいかな」と感じるような場合でも、早めに動物病院で詳しい検査を受けることが肝心です。近年はSpec cPL(犬膵特異的リパーゼ)検査や高感度の超音波検査など新しい診断技術の発達により、膵炎の状態をより正確に把握できるようになってきています。適切な検査と診断を受け、早期に対策することで合併症のリスクを減らし、愛犬のQOL(生活の質)を維持することが可能です。
急性膵炎はどのくらいで治るの?
急性膵炎は膵臓の炎症が急激かつ激しく起こった状態です。回復に要する時間は膵炎の重症度によって異なります。比較的軽症の場合は2~4日程度の入院治療で済み、退院後1~2週間ほどで完全に回復するケースもあります。しかし重度の急性膵炎では命に関わることもあり、数週間にわたる集中治療が必要になることがあります。
急性膵炎にはいわゆる「特効薬」のようなものはなく、治療の主体は支持療法(対症療法)になります。具体的には、輸液療法(点滴)によって脱水を是正し膵臓の血流を改善させること、鎮痛剤で激しい腹痛を和らげること、制吐剤で嘔吐を止めること、必要に応じて抗凝固剤でDIC(播種性血管内凝固)などの合併症を予防することなどが行われます。膵臓を安静にするため治療初期には絶食させますが、状態が安定してきたら低脂肪食を少量ずつ与え始めます。近年ではフザプラジブナトリウム水和物(商品名ブレンダZ)という膵炎治療用の抗炎症薬も登場し、膵臓の炎症を抑える目的で使われることがあります。基本的には急性膵炎の治療は入院下で点滴など集中的に行いますが、入院自体が強いストレスとなるような犬の場合、飼い主さんの協力のもとで毎日通院し皮下点滴や抗炎症薬の注射を行うといった形で治療を継続することもあります。
大切なことは、たとえ症状が重くても決してあきらめずに治療を続けることです。適切な治療に反応して膵炎が落ち着けば、犬の膵臓はダメージから回復し正常に機能するようになります。実際、ほとんどの犬は輸液療法と内科的管理によって急性膵炎から回復すると報告されています。急性膵炎そのものは完治しうる病気です。ただし、一度膵炎を起こした犬はその後も再発しやすい傾向があるため、再発予防のケアが重要になります。
慢性膵炎は治るの?治療にどれくらいかかる?
結論から述べると、慢性膵炎を完全に治すこと(治癒させること)は困難です。前述したように、慢性膵炎では膵臓組織が萎縮したり線維化(瘢痕化)するといった不可逆的変化が既に起こっているため、一度損なわれた膵臓の構造や機能が元通りになることは期待しにくいからです。そのため慢性膵炎の治療目的は、膵臓の炎症を抑えてこれ以上の悪化を防ぐこと、そして腹痛や嘔吐などの症状を和らげて犬のQOLを維持することにあります。言い換えると、慢性膵炎は「うまく付き合っていく」タイプの慢性疾患であり、完治させるというよりコントロールしていく病気と言えるでしょう。
慢性膵炎の治療法については後述しますが、中心となるのは内科療法による対症療法と食事療法(低脂肪食の給餌)です。膵臓の炎症や痛み・吐き気を薬で抑えながら、膵臓に負担をかけない低脂肪のフードで栄養管理することで、症状の安定化と膵臓の保護を図ります。これらの治療を根気強く続けることで、多くの慢性膵炎のワンちゃんは症状をうまくコントロールしながら生活していくことが可能です。ただし治療を中断したり管理を怠れば再び症状が悪化する恐れがあるため、継続的なケアが必要になります。
慢性膵炎が起こりやすい犬種・原因は?
犬の慢性膵炎は中高齢の犬で多く発症し、性別による差はないとされています。特定の犬種で発症が多いこともわかっており、以下の犬種は慢性膵炎(あるいは膵炎全般)を起こしやすいと報告されています。
- ミニチュア・シュナウザー: 脂質代謝異常(高脂血症)を起こしやすい遺伝的素因があり、高脂肪食による膵炎を発症しやすいとされています。実際、シュナウザーは膵炎患者の中で著しく過剰表現される犬種だとの報告もあります。
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル: 慢性膵炎、それも自己免疫性の膵炎を発症しやすい特殊な体質があるとされています。自己免疫性とは、自己の膵臓組織に対して免疫系が誤って攻撃を加えてしまうタイプの炎症です(ヒトの自己免疫性膵炎に似た疾患が犬のコッカーに認められています)。
- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、コリー、ボクサーなど: これらの犬種も慢性膵炎のリスクが高い可能性が示唆されています。特にキャバリアは組織学的に慢性膵炎の有病率が高いとの報告があります。
- トイ・プードル、ダックスフンド、ヨークシャーテリアなど: 急性膵炎を含め膵炎全般の好発犬種として、小型犬種でこれらの犬が挙げられることがあります。膵炎リスクは犬種の遺伝的背景にも関係すると考えられます。
もっとも、上記の犬種以外でも膵炎になる可能性は十分にあります。偏った食生活(高脂肪食の常用)や肥満など生活習慣の要因も慢性膵炎の発症に大きく関与すると考えられています。近年はドッグフード自体の品質向上により昔ほど脂肪過多な食事は減りましたが、それでも「おやつを与えすぎている」「人の食べ物の脂っこい部分を頻繁に与えている」などが重なると高脂血症や肥満を招き、膵炎のリスクが高まります。特に一度急性膵炎を起こした犬が、回復後にまた膵炎を再発し、それが慢性化するケースも多いので注意が必要です。
その他、慢性膵炎の誘因となりうるものには以下があります。
- 膵臓の外傷や腫瘍: 交通事故などでお腹を強打したり、膵臓に腫瘍ができたりすると膵炎を引き起こすことがあります。
- 特定の薬剤: 犬では確実な因果関係が判明している薬は多くありませんが、いくつかの薬剤は膵炎の引き金になりうると考えられています。報告されているものとしてはコリンエステラーゼ阻害剤、カルシウム製剤、臭化カリウム(抗てんかん薬)、L-アスパラギナーゼ(抗がん剤)、エストロジェン製剤、サリチル酸製剤、アザチオプリン、サイアザイド系利尿剤、ビンカアルカロイドなどがあります(これらは主に人医療での報告を基にしたリストですが、犬でも注意が必要です)。
- 内分泌疾患: 糖尿病、甲状腺機能低下症、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)といったホルモン疾患を持つ犬は膵炎を合併しやすいことが知られています。例えば糖尿病や甲状腺機能低下症では高脂血症になりやすく、それが膵炎のリスクになります。同様に副腎皮質機能亢進症(ステロイド過剰)は膵炎発症の報告がいくつかあります。
- その他: 細菌や寄生虫感染で膵炎が引き起こされるケースもまれにあります(犬ではバベシア症やリーシュマニア症との関連が報告されています)。また全身麻酔時の膵臓への低灌流(虚血)が原因で、術後に膵炎を発症することも指摘されています。以前は「手術そのものが膵炎のリスク」と言われましたが、現在では主に麻酔や循環管理の問題と考えられています。
以上のように、犬の膵炎(慢性膵炎)の発症には遺伝的素因と環境要因の両方が関与します。特定の犬種を飼っている場合は特に注意し、日頃から食事内容や体重管理に気を配ることが重要です。
慢性膵炎の診断は難しい!
慢性膵炎が厄介なのは、診断が容易ではない点にもあります。残念ながら慢性膵炎に特異的(これをやれば必ずわかるという)検査法は確立されていません。そのため総合的な判断や他疾患の除外によって診断を進めていく必要があります。
一般的に、慢性膵炎が疑われる場合には以下のような検査・評価を組み合わせて行います。
- 症状の評価: 先述の嘔吐・下痢・食欲不振など消化器症状の経過を詳しく問診し、腹部触診で痛みの有無など身体検査をします。
- 血液検査: Spec cPL(犬膵特異的リパーゼ)や膵特異的リパーゼ活性の測定を行い、膵炎の可能性を評価します。一般的な膵酵素(アミラーゼやリパーゼ)よりSpec cPLの方が膵炎に感度・特異度が高いとされています。ただし慢性膵炎では値が正常~軽度上昇程度に留まり、急性膵炎ほど顕著に上がらないこともあります。
- 画像診断: 腹部超音波検査で膵臓の形態変化を調べます。正常の犬では超音波で膵臓がはっきり描出されないことも多いですが、炎症や線維化が起こっている膵臓はエコーで明瞭に観察され、サイズの変化(腫大や萎縮)、輪郭の不整、周囲脂肪組織の変化などが確認できます。慢性膵炎では膵臓が硬く縮んでエコー上小さく映ることもあります。X線では膵臓自体は写りませんが、重度の場合に腹腔内の脂肪織濃度変化や腸管の位置異常として所見が出ることがあります。場合によってはCT検査で詳細に膵臓を評価することもあります。
- 膵臓生検: 確定診断を下すためには膵臓組織の病理検査(生検)が必要です。しかしながら犬で膵生検を行うには開腹手術または内視鏡手技が必要であり、麻酔リスクや出血リスクも伴うため実際に実施されることはほとんどありません。そのため、膵生検なしで他の検査結果を総合して診断するのが一般的です。
以上より、慢性膵炎の診断は除外診断(他の病気の可能性を消去していくことで消去法的に診断すること)と言われます。例えば腫瘍や他の炎症性腸疾患、肝胆疾患、異物誤飲など様々な病気を検査で否定しつつ、膵炎を示唆する所見(わずかな膵酵素の上昇やエコー所見など)を積み重ねて「慢性膵炎だろう」という結論に至るわけです。これは時間がかかる場合も多く、飼い主さんにとってももどかしいプロセスかもしれません。しかし診断精度を上げ適切な治療方針を立てるためには必要な過程です。近年の高感度検査の併用により診断の確度は上がってきていますが、それでも「慢性膵炎かもしれないが断定できない」という状況は少なくありません。慢性膵炎が疑われる場合には、根気強く獣医師と相談しながら検査・経過観察を続けることが重要です。
慢性膵炎の治療(内科療法・食事療法)
慢性膵炎は完治が難しい病気ですが、適切な治療と管理によって症状をコントロールし、合併症を予防することができます。治療の中心は内科的な対症療法と食事療法(低脂肪食)です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
内科療法による対症療法(痛み・炎症・吐き気などのコントロール)
慢性膵炎の治療でまず重要なのは、犬にとってつらい症状を緩和してあげることです。特に強い腹痛がある場合、速やかに取り除いてあげる必要があります。膵炎による腹痛は犬の生活の質を著しく低下させてしまうためです。鎮痛剤としてはブトルファノール、ブプレノルフィン、トラマドールなどのオピオイド系鎮痛薬がよく用いられます。必要に応じてNSAIDs(非ステロイド系抗炎症薬)が使われることもありますが、膵炎ではNSAIDsは効果が限定的なうえ腎臓や胃腸への副作用も懸念されるため、一般には麻薬系鎮痛薬が選択されます。
膵炎に伴う嘔吐が続いている場合には、制吐剤で吐き気を抑えます。代表的な薬はマロピタント(商品名セレニア)で、中枢に作用して強力に嘔吐を止めてくれます。必要に応じてメトクロプラミド(プリンペラン)など他の制吐薬を併用することもあります。また下痢が続く場合には、腸粘膜を保護したり腸の動きを整える薬を使います。整腸剤(乳酸菌や酵母などのプロバイオティクス製剤)や消化管運動調整薬を投与し、症状に合わせて下痢止め(処方食の繊維やロペラミド製剤など)で対応します。日本では動物用医薬品として次硝酸ビスマス+タンニン酸アルブミン合剤(商品名ディアバスター)や植物抽出成分を含む下痢止め(デルクリアなど)が使用されることがあります。これらは腸内ガスや毒素の吸着、腸粘膜保護作用によって下痢を軽減します。
慢性膵炎では炎症そのものを抑えることも重要です。膵炎の炎症が自己免疫性(免疫介在性)の場合、ステロイド剤の投与によって症状の改善が見られたとの報告があります。特にイングリッシュ・コッカー・スパニエルの慢性膵炎は免疫介在性が示唆されており、ステロイド治療が有効なケースがあります。ただしステロイドは血栓症(血が固まりやすくなる)を引き起こしたり、糖尿病を悪化させるなどの副作用もあるため慎重に適応を判断する必要があります。また、ステロイドの代替として免疫抑制剤のシクロスポリンを用いることで自己免疫性の慢性膵炎をコントロールできたという報告もあります。シクロスポリンはステロイドに比べて糖代謝への影響が少なく、副作用の面で安全性が高い利点があります。ただし高価な薬であること、免疫を抑えることで感染症リスクが上がることなど注意点もあります。
そのほか、膵臓から漏れ出た消化酵素が体を傷つけるのを防ぐために蛋白分解酵素阻害剤(例えばガベキサートメシル酸塩など)を点滴に加えることがあります。また将来的に膵外分泌不全が懸念される場合や、消化を助けて膵臓の負担を減らす目的で消化酵素補充剤(膵酵素剤)を用いることもあります。消化酵素剤は膵臓が産生する酵素(リパーゼやアミラーゼ、プロテアーゼ)を補充する粉末製剤で、食事に混ぜて与えます。これにより膵臓自身が分泌する酵素量を減らし、膵臓の仕事を少し楽にしてあげる効果が期待されます。
いずれにしても、慢性膵炎の内科治療は症状を抑えつつ膵臓を守るSupportive careが主体です。場合によっては定期的な補液や投薬を継続し、病状の進行をモニターしながら治療内容を調整していきます。長期管理が必要な病気ですが、定期検査と適切な投薬で多くのワンちゃんは安定した生活を取り戻しています。
低脂肪食による食事療法がカギ
食事療法は慢性膵炎の管理において極めて重要です。膵臓への負担を減らすには、何と言っても日々の食事内容を見直す必要があります。具体的には低脂肪食への切り替えが推奨されます。
ポイントはフード中の脂肪分を極力抑えることです。目安としては、フードの乾物重量あたりで7%以下の脂肪を含む食事が望ましいとされています。ドッグフードの成分表示では「粗脂肪○%」と水分含有下で記載されていますが、水分量を考慮して乾物ベース(ドライマター)に換算する必要があります。例えばウェットフードのラベルに粗脂肪4%と書いてあっても、水分含有量が約76%であれば乾物中の実際の脂肪率は約16%にもなります(4 ÷ (100-76) × 100=16%)。このように一見低脂肪に思えるフードでも、乾物で見るとそれほど低くないことがあるので注意しましょう。
一般的に市販の療法食として「消化器サポート」「低脂肪」などと銘打たれたドライフードやウェットフードは、乾物あたり7~10%程度まで脂肪を抑えて設計されています。例えばロイヤルカナンの低脂肪フードでは乾物中10%未満、ヒルズのi/dローファットなども7~10%程度になっています。症状が強い場合や高脂血症を伴う場合はより厳格に脂肪制限(乾物中5~7%以下)が必要なこともあります。
低脂肪のドッグフードを選ぶ際は、原材料のお肉にも注目すると良いでしょう。比較的脂肪分の少ないタンパク源として鶏ささみや鹿肉(ベニソン)、馬肉、ラム肉などが使われているフードがおすすめです。これらの肉類は牛肉や豚肉に比べて脂肪含有率が低く、良質なタンパク質を摂取できます。また製品によってはMCT(中鎖脂肪酸)のように消化吸収されやすい脂肪を使うことで膵臓への負担を減らしているものもあります。
もし手作り食で低脂肪の食事を与えたい場合は、鶏のささみや白身魚(タラやヒラメなど)といった低脂肪・高タンパクの食材をベースに、エネルギー補給源として少量の炭水化物(サツマイモやかぼちゃ、白米など)を加えると良いでしょう。野菜類も繊維源として少量加える分には問題ありません。ただし手作りの場合、栄養バランスが偏りやすいため長期に続けるのは難しい面があります。必要に応じて管理栄養士や獣医師に相談しながら進めることをおすすめします。
さらに注意したいのが穀類(炭水化物)の扱いです。小麦(パンなど)や大豆、トウモロコシといった穀物は、もともと犬にとって消化がやや難しい食品です。健常な犬でも穀物由来の下痢を起こすことがありますが、膵炎の犬では消化酵素が不足している分、穀物の消化は一層困難になります。そのため小麦粉たっぷりのパンや麺類、大豆製品、トウモロコシなどはあまり与えない方が良いでしょう。炭水化物源として与えるにしても、白米やかぼちゃ、芋類など比較的消化に問題の少ないものを選び、量も控えめにします。
膵炎の犬に適した食べ物のポイント
低脂肪であること以外に、「膵炎の犬に良いフード」の条件としてどんなものがあるでしょうか?いくつかポイントを挙げてみます。
- 高繊維: 適度に食物繊維を含む食事は、腸内環境の改善や血糖値の急上昇抑制に役立ちます。膵炎の子では便通を整えたり、二次的な肥満防止のためにも食物繊維が豊富なフードが良いでしょう。
- 低GI(低糖質): 炭水化物源は血糖値の上がりにくい低GIのものを選ぶとベターです。精製穀物よりも雑穀やイモ類を使ったレシピなどが望ましいです(糖尿病予防の観点から)。
- 高品質で消化の良いタンパク質: 量は制限しつつも、タンパク質は犬にとって必要不可欠な栄養素です。質の良い動物性タンパクを含み、消化吸収されやすいフードが望ましいです。魚由来のタンパク質はアミノ酸バランスも良く消化性も高いです。
- 抗炎症成分の含有: オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)や一部のハーブ類には抗炎症作用があり、慢性膵炎による炎症軽減に役立つ可能性があります。実際、魚油由来のオメガ3脂肪酸は体内の炎症反応を抑制し免疫機能を調整する働きが報告されています。こうした成分が配合されているフードやサプリメントは膵炎管理の補助となりえます。
以上を踏まえ、次の章では獣医師の視点から膵臓に配慮したおすすめのドッグフードを紹介します。
獣医師おすすめ:膵臓に良い低脂肪フード
慢性膵炎の管理には適切な食事選びが欠かせません。しかし実際には「どんなフードを選べばいいかわからない」「低脂肪フードを試したが食いつきが悪い」「フードを変えても膵炎を繰り返してしまう」と頭を抱える飼い主さんも多いのではないでしょうか。
理想的なフードに出会うことができれば、愛犬の膵炎症状が改善・安定するのはもちろん、食事への満足度が上がることで不要なおやつを与えずに済み、さらにフード自体の機能で膵炎になりにくい体質へ改善されていきます。その結果、膵炎の再発リスクを大きく減らすことが期待できます。
では、そんな理想的なフードとはどんなものでしょうか?獣医師の立場から考える「膵臓に優しいフード」の条件は次の3点です。
- 十分に低脂肪で膵臓に負担をかけないこと
- 膵炎になりにくい体質へ改善する作用があること
- 嗜好性が高く、食いつきが良いこと
上記3つを満たすフードこそ、膵炎の愛犬にとって最良の療法食と言えます。ここでは、これらの条件を満たすよう厳選したおすすめの低脂肪ドッグフードを紹介します。
🐕 膵炎ケア用製品 総合おすすめ早見表
📦 ドライフード部門
| 順位 | 商品名 (ブランド) | フードタイプ | 脂質含有量 | 主要成分・特徴 | 価格帯 | 購入先 | 総合 オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和漢みらいのドッグフード 【特別療法食(膵臓用)】 (犬心) | 特別療法食 | 7%以下 | 鹿肉、和漢素材89種類 マクロビ発酵素材 オメガ3脂肪酸 ファイトケミカル | 高級 | 公式サイト 一部動物病院 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🥫 ウェットフード部門
| 順位 | 商品名 (ブランド) | 特徴・成分 | 容量・価格 | 購入先 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ヒルズ プリスクリプション・ダイエット i/d ローファット チキン&野菜入りシチュー | 高消化性タンパク質 ショウガ・オメガ3配合 抗酸化成分強化 | 354g×12缶 約8,000-10,000円 | 動物病院 通販サイト | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2位 | ロイヤルカナン 消化器サポート(低脂肪)ウェット缶 | 高消化性設計 プレバイオティクス 複数食物繊維配合 | 200g×12缶 約6,000-8,000円 | 動物病院 ペット薬局 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 3位 | ロイヤルカナン 消化器サポート 高栄養リキッド | 高エネルギー設計 中鎖脂肪酸使用 必須栄養素強化 | 200ml×3本 約3,000-4,000円 | 動物病院 | ⭐⭐⭐⭐ |
💊 サプリメント部門
| 順位 | 商品名 (ブランド) | 主要成分・効果 | 容量・価格 | 購入先 | オススメ度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | マイトマックス・スーパー | ペディオコッカス菌 腸内環境改善 特殊カプセル技術 | 60カプセル 約4,000-5,000円 | 動物病院 獣医師推奨 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
🔍 愛犬の状況別 最適組み合わせガイド
🚨 急性膵炎からの回復期
推奨組み合わせ:
- メイン: ヒルズ i/d ウェット ⭐⭐⭐⭐⭐
- 補助: ロイヤルカナン リキッド ⭐⭐⭐⭐⭐
- サプリ: マイトマックス ⭐⭐⭐⭐
理由: 消化しやすく、栄養価が高い。食欲不振時も摂取しやすい
🔄 慢性膵炎の長期管理
推奨組み合わせ:
- メイン: 和漢みらいドライ ⭐⭐⭐⭐⭐
- トッピング: ロイヤルカナンウェット ⭐⭐⭐⭐
- サプリ: マイトマックス ⭐⭐⭐⭐⭐
理由: 体質改善効果と腸内環境ケアで再発予防
😤 食いつき改善重視
推奨組み合わせ:
- メイン: 和漢みらいドライ ⭐⭐⭐⭐⭐
- 嗜好性UP: ヒルズ i/d ウェット ⭐⭐⭐⭐⭐
理由: 両製品とも嗜好性が高く評価されている
🏥 重篤・衰弱状態
推奨組み合わせ:
- 緊急栄養: ロイヤルカナン リキッド ⭐⭐⭐⭐⭐
- 段階移行: ヒルズ i/d ウェット → 和漢みらいドライ
和漢みらいのドッグフード【特別療法食(膵臓用)】
まずご紹介するのは、製薬会社が開発した高機能ドッグフード「和漢みらいのドッグフード 特別療法食(膵臓用)」です。名前の通り和漢(漢方)の知見を取り入れた特別療法食で、膵炎の子に配慮した処方になっています。
このフードの大きな特徴は、以下のような他に類を見ない豊富な有用成分が含まれていることです。
- 膵臓に良い漢方素材を89種類配合: ウコンやマリアアザミ、柴胡、甘草など伝統的に肝臓・消化器をケアするとされる多数の和漢ハーブが含まれています。膵臓そのもののケアだけでなく、体全体の調子を整える目的があります。
- 高品質な鹿肉を使用: 良質なたんぱく源としてニュージーランド産の鹿肉が主原料に使われています。鹿肉は高タンパクで低脂肪な上、アレルギーになりにくいメリットもあります。
- 腸内環境を整えるマクロビ発酵素材を配合: 乳酸菌発酵させた玄米や大豆、野菜などの植物発酵エキスが含まれ、腸内の善玉菌をサポートします。腸内環境の改善は膵炎の再発予防にも大切です。
- オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)を含有: 青魚由来のオメガ3が配合されており、抗炎症作用によって膵臓の慢性的な炎症を抑える効果が期待できます。
- ファイトケミカル豊富: ポリフェノールやカロテノイドなど植物由来の抗酸化成分も多数含まれ、細胞の酸化ストレスを軽減します。
このように愛犬の体に良い成分が盛りだくさんのフードで、膵臓のケアはもちろん根本的な体質改善まで視野に入れて作られている点が大きな魅力です。漢方素材がふんだんに使われていますが、副作用の心配はなく、長期給餌にも適しています。
さらに食いつきが非常に良いことも飼い主さんから高く評価されています。療法食というと食いつきの悪さが心配になりますが、和漢みらいのドッグフードは原材料に徹底的にこだわり嗜好性を高めているため、美味しさと栄養を両立しています。「普段フードをなかなか食べない子でもガツガツ食べてくれた」という声も多く、食が細いワンちゃんやシニア犬にも試す価値があります。
もちろん低脂肪設計も徹底されています。和漢みらい膵臓用は低脂質・低糖質・無添加にこだわったヒューマングレード品質で、脂質は乾物ベースで7%以下、炭水化物も低GIの食材中心、人工添加物は一切使用していません。まさに膵臓に優しい処方と言えます。
実際にこのフードを使用している飼い主さんからは、次のような口コミが寄せられています。
- 飽きずに食べてくれています(20代女性): イヤイヤが多い我が家の老犬も色々試しましたが、和漢のフードは飽きずに食べてくれています。やっと継続して食べてくれるフードにたどり着きました!血液検査の値も横ばいで、悪化せず維持できています。
- 低脂肪フードの中で一番の食いつきです(40代女性): これまで低脂肪のフードを色々試しましたが、うちの子にはこれが一番合いました。他のフードはあまり食べず仕方なく食べる感じでしたが、和漢みらいは毎回ガツガツと夢中で食べてくれます。
- 高齢犬にもぴったり(60代女性): 19才なので膵臓の機能も低下しており、食べやすいフードを探していました。他のフードにふりかけのように少量混ぜて与えたところ、違和感なく完食してくれました。おかげで体調も安定し、めざせ20才です!
このように、膵炎に悩む愛犬と飼い主さんから高い評価を受けているフードです。慢性膵炎で苦しむワンちゃんにはぜひ試してみてほしい一品と言えるでしょう。
おすすめの低脂肪ウェットフードランキング3選
続いて、食欲の落ちた犬やトッピング用にも使いやすい低脂肪ウェットフードのおすすめを3つ紹介します。どれも獣医師からの評判が高い療法食です。
1. ヒルズ プリスクリプション・ダイエット i/d ローファット チキン&野菜入りシチュー (缶)
ヒルズ社の消化器サポート食「i/d ローファット」の缶タイプです。特徴は以下の通りです。
- 優れた消化性と低脂肪: 高消化性のタンパク質を使用し、脂肪分を大幅に抑制。膵炎で乱れた消化を助けます。
- ショウガ・オメガ3脂肪酸を配合: ショウガは伝統的に消化を助け吐き気を抑える効果が期待され、オメガ3は抗炎症作用で膵炎の炎症軽減に寄与します。
- 科学的に証明された抗酸化成分: ビタミンEやCなど抗酸化ビタミンが強化されており、炎症による組織ダメージを和らげます。
- ミネラルバランス: 膵炎時に二次的に起こりやすいミネラルバランスの乱れに配慮し、電解質などが調整されています。
なによりとても美味しく食いつきが良いのが魅力です。柔らかいシチュー状で、一口大のチキンやお米、ニンジン・ホウレンソウなどが入っており、匂いも良いため食欲が落ちた子でも食べやすいでしょう。「低脂肪食が必要だけどドライは食べない…」という膵炎の犬に最適です。
2. ロイヤルカナン 療法食 消化器サポート(低脂肪) ウェット缶
ロイヤルカナンの低脂肪ウェットフードです。特徴は以下の通りです。
- 高消化性: 消化管の健康維持に配慮して高消化性に設計されており、さらにプレバイオティクスを含む複数の食物繊維をバランスよく配合しています。お腹に優しく、下痢の改善にも役立ちます。
- 低脂肪: 脂肪含有量を厳格に調整し、脂肪制限が必要な犬に適した処方になっています。脂質代謝に不安のある犬でも安心です。
- 適度な食物繊維: 低脂肪でも必要なカロリーを摂取できるように、食物繊維の量と種類を調整しています。お腹が膨れやすいわりに太りにくい処方です。
この「消化器サポート低脂肪」缶は、消化吸収不良による下痢や高脂血症の犬に給餌する目的で特別に調製された療法食です。香りや舌触りも工夫されており、食欲をそそるパテ状になっています。脂肪分を抑えつつも必要なエネルギーや栄養素はしっかり補給できるバランスの良いフードです。
3. ロイヤルカナン 消化器サポート 高栄養リキッド (クリティカルリキッド GI ハイエナジー)
こちらもロイヤルカナンの療法食で、液状タイプの流動食です。食事を自力で十分に摂れない回復期の犬に給与する目的で調製されており、急性膵炎からの復復期や慢性膵炎で衰弱した場合などに適しています。特徴は以下の通りです。
- 高エネルギー設計: 少量で効率良くカロリーを摂取できるよう高濃度エネルギーに調整されています。食べられる量が限られる子でも必要エネルギーを補給できます。
- 低脂肪: 脂肪含有量を低く抑え、膵臓への負担を軽減しています(脂質の一部には中鎖脂肪酸など消化吸収しやすいものを使用)。
- 必須栄養素を強化: ビタミンやミネラル、アミノ酸などが強化配合され、少量でも栄養バランスを維持できます。
- 高消化性原材料: 消化吸収の良い原材料のみを使用し、弱った消化管でも効率良く栄養が取り込めます。
本品はシリンジやチューブで強制給餌することも想定された流動食ですが、風味が良く自力でも飲みやすいため、スープ感覚で与えることもできます。「体力をつけさせたいが固形物は受け付けない」という場合に非常に役立ちます。
おすすめのサプリメント:プロバイオティクスなど
膵炎を繰り返すワンちゃんでは、もともと腸内環境が乱れている子も少なくありません。慢性膵炎の管理では膵臓だけでなく腸の健康にも目を向ける必要があります。腸内環境を整えるには、整腸剤(プロバイオティクス)のサプリメントを活用すると良いでしょう。
獣医師がおすすめする腸活サプリの一つが「マイトマックス・スーパー」です。これは従来のビフィズス菌や乳酸菌とは異なるペディオコッカス菌という有用菌を主成分としたペット用プロバイオティクス製品です。
マイトマックス・スーパーの優れている点は、特殊カプセル技術により生きたまま有益菌が腸まで届くことです。摂取後すみやかに小腸・大腸に定着して善玉菌を増やし、乱れた腸内細菌バランスを速やかに整える効果があります。抗生物質などによる副作用もなく安全性が高いので、長期で飲ませることも可能です。
実際、慢性的な軟便や下痢、食物アレルギーによる腸炎などに悩む犬でマイトマックスを使用すると、数日で便の状態が改善するケースが多く報告されています。また動物病院でも処方されることが多く、獣医師御用達の整腸サプリとも言えます。慢性膵炎のワンちゃんでは膵酵素分泌低下から軽度の消化不良が起こりやすく、それによって腸内環境が悪化しがちです。マイトマックス・スーパーを併用することで腸を整え、結果的に膵炎の再発リスクを下げる効果が期待できます。
なお、慢性膵炎の管理には他にもビタミンB群や抗酸化サプリ(ビタミンE/C、コエンザイムQ10など)、消化を助ける酵素サプリなどが有用な場合があります。ただ、サプリメントはあくまで補助であり、まずは主食となるフードの見直しと内科治療が優先です。サプリを取り入れる際は獣医師に相談し、愛犬の状態に合ったものを選ぶようにしましょう。
慢性膵炎になったワンちゃんの寿命はどのくらい?
| 要因 | 寿命への影響 | リスク度 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 慢性膵炎そのもの | 軽度~中程度 | 中 | 直接的な生命への脅威は低い |
| 合併症の併発 | 重大な影響 | 高 | 最も寿命に影響する要因 |
| 急性膵炎の再発 | 重大な影響 | 高 | 重症例では致死率20-40% |
| 適切な管理下 | 影響軽微 | 低 | 年齢相応の天寿を全うできる |
愛犬が慢性膵炎と診断されると、「寿命は縮まってしまうのか?」と心配になる飼い主さんも多いでしょう。
一般に慢性膵炎の犬は、健康な犬と比べて平均寿命が短くなる傾向があると報告されています。これは慢性膵炎そのものというより、前述した合併症(糖尿病、膵外分泌不全、腎不全など)を併発しやすいためです。例えば膵炎由来の糖尿病になればインスリン治療が一生必要になりますし、膵外分泌不全になれば消化不良による体重減少や下痢と闘い続けることになります。慢性膵炎の犬はこうした慢性的疾患を複数抱えるリスクがあるため、結果的に寿命へ影響しうるのです。
また、慢性膵炎の犬は急性膵炎の再発にも注意が必要です。慢性膵炎がある犬は膵臓が弱っている分、何かの拍子で急激に炎症が悪化し重度の急性膵炎を起こすことがあります。急性膵炎は重症度によって致死率が大きく異なりますが、重症例では20~40%前後が死亡するとの報告もあります。実際、専門医療機関に紹介されるような重度急性膵炎では50%近い死亡率が報告されたケースもあります。したがって慢性膵炎の子が急性膵炎を起こさないよう管理することが非常に大切です。
もっとも、慢性膵炎と診断されたからといって直ちに余命いくばくもない…というわけでは決してありません。適切な治療とケアで寿命を全うした例もたくさんあります。重要なのは膵炎を抱えつついかに上手に生活の質を保ってあげるかです。慢性膵炎の犬は一生何らかの炎症がくすぶる可能性がありますが、しっかりコントロールすれば低空飛行ながら安定した体調を維持できると考えられています。実際のところ慢性膵炎の予後(寿命)に関して大規模なデータはありませんが、多くの場合は合併症さえ防げれば年齢相応に天寿を全うできると考えてよいでしょう。
飼い主さんにできることは、愛犬の体調の変化を見逃さず早め早めに対応することです。定期的に血液検査や超音波検査を受け、膵炎の状態や合併症の有無をチェックしましょう。体重の減少や多飲多尿、便の性状変化など気になることがあればすぐに獣医師に相談してください。適切な管理の下で、慢性膵炎のワンちゃんも穏やかで幸せなシニアライフを送ることは十分可能です。
慢性膵炎にはオメガ3脂肪酸サプリメントがおすすめ
慢性膵炎の管理において、栄養補助としてオメガ3系脂肪酸(フィッシュオイル)のサプリメントを追加することは有益とされています。オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)は抗炎症作用を持つため、膵臓の慢性的な炎症を和らげる効果が期待できます。具体的には、EPA/DHAは体内で炎症を促進する物質(ロイコトリエンやサイトカイン)の産生を抑制し、炎症を穏やかにする働きがあります。
またオメガ3脂肪酸には免疫機能の調整作用もあります。慢性膵炎では膵臓に対する免疫系の過剰反応が炎症を悪化させている可能性があります。オメガ3は免疫細胞の膜構成成分となり、その機能に影響を与えることで過剰な免疫反応を抑制すると考えられています。その結果、慢性膵炎の症状緩和や進行抑制に寄与しうるのです。
実際、重度の急性膵炎の治療において静脈内投与のフィッシュオイル脂肪酸が炎症反応を軽減し免疫機能を改善したとの報告もあります。慢性膵炎であっても、日常的にEPA/DHAを適量摂取させることで膵臓の炎症状態を穏やかに保つ効果が期待できます。市販の犬用フィッシュオイル製品(サーモンオイルなど)をフードに数滴かけて与えるだけでも違うでしょう。
ただし脂肪酸である以上カロリーもあるため、与えすぎは禁物です。一般的にはEPA+DHAの合計で体重10kgあたり約700mg/日程度が治療的量とされています。市販カプセル製剤の場合は製品表示を確認し、適量を守って与えてください。過剰に与えると軟便になったり、逆に膵臓に負担となる可能性もありますので要注意です。適切な用量であればオメガ3脂肪酸は安全性が高く、副作用もほとんどないため、慢性膵炎の犬にはぜひ取り入れたいサプリメントと言えます。
まとめ
最後に、本記事の重要ポイントをまとめます。
- 慢性膵炎は完治しない消化器疾患ですが、適切な管理により症状をコントロールしながら生活することが可能です。
- 慢性膵炎は膵炎発作が繰り返されることで膵臓の細胞が破壊され、膵組織の萎縮・線維化を招いて機能低下を起こす病気です。 一度壊れた膵臓組織は元に戻らないため、進行を止めることが治療の目標になります。
- 慢性膵炎では糖尿病や膵外分泌不全などを併発することがあり、これらへの対処も必要です。 合併症が発生すると管理はさらに複雑になるため、そうなる前に膵炎をコントロールすることが望ましいです。
- 慢性膵炎の診断は簡単ではなく、除外診断によって行われます。 他の疾患を除外しつつ、症状・血液検査・画像検査の所見を総合して判断します。確定診断には膵生検が必要ですが侵襲的なため、通常は行われません。
- 治療は内科的対症療法(痛み・炎症・嘔吐のコントロールなど)と食事療法が中心です。 鎮痛剤や制吐剤を用いて症状を緩和し、必要に応じて免疫抑制剤や酵素補充剤も使います。食事は低脂肪食に切り替え、膵臓への負荷を減らします。
- 低脂肪食の給餌は膵炎管理の要です。 可能な限り脂肪分を抑えたフードを与え、高脂肪のおやつや人の食べ物は厳禁とします。肥満にならないよう体重管理と適度な運動も重要です。
- 膵炎管理に有用なフードやサプリを活用しましょう。 例えば「和漢みらいの膵臓用フード」は漢方入りで体質改善も期待できる低脂肪食ですし、プロバイオティクスサプリやオメガ3脂肪酸は炎症抑制や消化補助に有益です。
- 慢性膵炎自体は命に直結する病気ではありませんが、一生涯のケアが必要な病気です。 焦らず根気よく向き合うことが大切になります。
- 膵炎の悪化を防ぐには早期発見・早期治療が重要です。 軽い症状の段階で気づいてあげられれば、その分膵臓のダメージを抑え、合併症を未然に防ぐことができます。
- 治療では痛みの緩和や栄養管理に加え、普段の生活でストレスを減らすことも大切です。 ストレスは免疫やホルモンバランスを乱し、膵炎を悪化させる一因になりえます。生活環境を整え、安静と適度な運動のバランスをとってあげましょう。
- 定期的な健康診断(血液検査や超音波検査)を受け、病状の変化をチェックしてもらうことも欠かせません。 医学記事では膵炎の見直しは半年~1年ごとに行うことが推奨されています。
慢性膵炎と聞くと不安になるかもしれませんが、正しい知識と対策があれば怖がる必要はありません。愛犬の様子をしっかり観察し、獣医師と二人三脚で治療とケアを続ければ、きっと穏やかな日常を取り戻せるはずです。飼い主さんと愛犬の「チーム effort」で、膵炎に負けない生活を目指しましょう。すでに慢性膵炎と指摘されている飼い主さんも、どうかあきらめずに考えられる限りの対策を組み合わせて愛犬を支えてあげてください。もちろん私たち獣医師も全力でサポートします。一緒に頑張っていきましょう!
