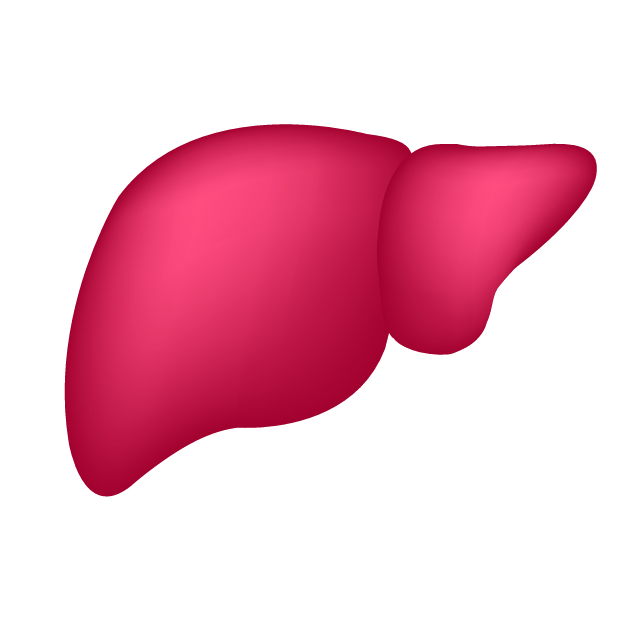
病院の健康診断で愛犬の血液検査をしたら、肝臓の数値が高いと指摘されて心配になったことはありませんか?「さつまいもが肝臓に良い」という話を耳にして、ビタミン剤やサプリメントを急いで購入しようと考えている飼い主さんもいるかもしれません。しかし、まず落ち着いてください。肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、初期にはほとんど症状を示さない臓器です。肝臓の数値が高い原因や肝臓に良い食べ物・悪い食べ物を正しく理解し、愛犬にとって最善のケアを選ぶことが大切です。この記事では、獣医師かつペット栄養管理士の視点から、エビデンスに基づいた肝臓ケアの情報をわかりやすく解説します。
ポイント: 肝臓の数値が高いからといって必ずしも肝臓の病気とは限りません。まずは何が原因で数値が上がっているのか見極めましょう。さらに、さつまいもをはじめとする肝臓に良い食べ物や、逆に避けるべき悪い食べ物についても詳しく解説します。愛犬の健康を守るために、ぜひ最後までお読みください。
肝臓にはさつまいもが良いって本当?
結論から言えば、さつまいもは肝臓の健康に役立つ食材の一つです。ただし、「さつまいもを食べれば肝臓の数値が下がる」結論から言えば、さつまいもは肝臓の健康に役立つ食材の一つです。ただし、「さつまいもを食べれば肝臓の数値が下がる」といった即効性のある「治療薬」ではありません。あくまで肝臓に負担をかけにくい栄養豊富な食品として、食事療法の一環に取り入れる価値があるという位置づけです。
さつまいもが肝臓に良いとされる理由はいくつかあります。
・食物繊維が豊富で消化を助ける: さつまいもの豊富な食物繊維は腸内環境を整え、便秘や下痢の改善に役立ちます。肝臓病の犬では消化不良や便通の乱れが起こりやすいですが、食物繊維により腸内の老廃物排出が促され、結果的に肝臓の負担軽減につながると期待されます。
・βカロテンなど抗酸化物質による肝細胞保護: さつまいもにはβ-カロテンやビタミンC・Eなど抗酸化作用のある栄養素が含まれています。肝臓は解毒の過程で活性酸素などストレスを受けやすい臓器ですが、抗酸化成分がそれらによる肝細胞の損傷を防ぐ助けになります。
・ビタミンB6によるタンパク代謝サポート: さつまいもはビタミンB群(特にB6)も豊富で、タンパク質の消化吸収を助けます。肝臓でのタンパク代謝を効率化し、肝機能の向上や肝酵素値の改善に役立つ可能性があります。
・低脂肪でカロリー控えめ: さつまいもは脂肪分が少ない食品です。肝臓は脂肪の代謝も担いますが、過剰な脂肪摂取は肝臓に脂肪が蓄積したり負担となることがあります。さつまいものような低脂肪食品は肝臓への負担軽減に適しています。
以上のように、さつまいも自体は安全で健康的な食材であり(※犬には加熱調理したものを与えてください。生のままでは消化不良や下痢・嘔吐の原因になります)、適量であれば肝臓ケアの食事に取り入れる価値があります。ただし大前提として、愛犬の具体的な病状に応じた対応が必要です。例えば肥満気味や糖尿病の犬には、さつまいもの与えすぎは禁物です。さつまいもは炭水化物が多くカロリーも高いため、過剰に与えると肥満や血糖値の上昇につながります。結石(シュウ酸カルシウム結石)を起こしやすい犬では、さつまいも中のシュウ酸塩がリスクとなる可能性があるため控えるのが望ましいでしょう。また、肝臓病の種類によってはさつまいもを避けた方が良い場合もあります。特に銅蓄積性の慢性肝炎では、さつまいもに含まれる微量の銅でも蓄積を助長する可能性が指摘されています。実際、手作り食でレバーや赤身肉、さつまいも、納豆などを安易に与えると、銅の過剰摂取により肝臓病の進行を早める恐れがあると報告されています。
まとめると: さつまいもは肝臓に良い栄養素を多く含むため、肝臓ケア食材として「適量を正しく与えれば」有用です。ただし、愛犬の体質や病態によっては量に注意し、必ず加熱したものを与える、持病がある場合は事前に獣医師に相談する、といった配慮が必要です。 さつまいもだけに頼るのではなく、後述するような総合的な食事療法や適切な治療と組み合わせることで、初めて肝臓の数値改善や病状コントロールに効果が期待できることを覚えておきましょう。
肝臓の数値とは?(肝酵素の基礎)
「肝臓の数値が高い」とは主に血液中の肝酵素値の上昇を指します。獣医師から「肝臓の数値が悪い」と言われた場合、具体的にはALT(GPT)やAST(GOT)、ALP、GGTといった肝酵素の測定値に基準値より高い異常が見られることを意味します。これらの項目は肝臓や胆管の状態を反映する代表的な指標で、健康診断でもチェックされます。
大切なのは、肝酵素値が高いからといって即肝臓の病気と断定はできない点です。肝酵素は肝臓以外の臓器・組織からも放出されるため、筋肉疾患やホルモン疾患、ストレスなどでも変動しうるのです。例えばクッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)ではホルモンの影響でALPが顕著に上昇しますし、甲状腺機能低下症でもコレステロールや肝酵素が上がることがあります。また胆嚢炎や膵炎など隣接臓器の炎症でも二次的に肝酵素が上がる場合があります。このように、肝酵素上昇=肝臓が悪いとは限らないため、血液検査の結果は臨床症状や追加検査(超音波検査やレントゲン等)と合わせて総合判断することが重要です。
では肝酵素それぞれが何を意味するのか、基礎知識を整理しておきましょう。
ALT(アランインアミノトランスフェラーゼ)
ALT(GPTとも呼ばれます)は肝臓の肝細胞内に最も多く存在する酵素です。肝細胞が傷害を受けて破壊されると血液中に漏れ出す「逸脱酵素」の一つで、肝細胞へのダメージを敏感に反映する指標として用いられます。急性・慢性を問わず肝炎や脂肪肝などでALT上昇が見られ、特に慢性肝炎ではALTの上昇が初期から認められる最も鋭敏な異常であると報告されています。
ALTが基準値より高い場合の解釈: 肝臓に炎症や壊死が起きている可能性があります。ただし一過性の軽度上昇で症状がなければ経過観察となることもあります。2倍以上の持続的上昇や症状を伴う場合には、慢性肝炎などの疑いで精査が必要です。
AST(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ)
AST(GOT)もALTと同様に肝細胞の障害で逸脱する酵素です。ALTと異なるのは、ASTは肝臓以外に筋肉や赤血球にも含まれる点です。そのため重度の筋肉疾患や溶血(赤血球破壊)でもAST上昇が起こりえます。また、一部の薬剤投与によってもASTが急上昇することが報告されています。
AST上昇の解釈: ALTとASTがともに高い場合は肝臓由来の障害の可能性が高まります。一方、ALT正常でASTだけ高い場合は筋肉由来(例:外傷や激しい運動後、心筋障害など)を疑います。ASTは半減期が短く変動しやすいため、ALTほど肝臓特異性は高くありませんが、肝障害の有無を補助的にみる指標となります。
ALP(アルカリフォスファターゼ)・GGT(ガンマグルタミルトランスフェプチダーゼ)
ALPおよびGGTは主に胆管や胆汁うっ滞に関連して上昇する酵素です。ALPは肝臓以外にも骨や腎臓など様々な組織で作られますが、犬では肝臓由来のALPアイソザイムが存在し、ステロイドホルモンによって誘導される特徴があります。そのため、副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)やステロイド投薬によって犬のALPは著しく高値になることがよくあります。また成長期の子犬では骨の成長に伴ってALP高値を示すことがあり、これは生理的な上昇で病的意義はありません。
GGTは胆管上皮に多く存在する酵素で、胆管や胆汁うっ滞の状態を反映する指標です。GGT単独で大幅上昇するケースは少ないですが、ALPと並行して上がっている場合は胆管閉塞や胆泥症など胆道系トラブルの可能性を考えます。なお、猫では肝脂肪症でALP↑GGT→(正常か軽度↑)というパターンがありますが、犬では一般的にALPとGGTは共に上昇する傾向があります。
ALP/GGT上昇の解釈: ALTやASTが正常でALP/GGTだけ高い場合、胆嚢炎や胆石など胆汁うっ滞やホルモン異常(クッシング症候群)を疑います。肝臓そのものより周辺臓器や全身状態の影響で反応性に上がっている可能性もあります。逆にALT/ASTも同時に高い場合は、肝細胞障害と胆汁うっ滞の両面がある(例えば重度の肝炎で二次的に胆汁うっ滞を起こしているなど)ことも考えられます。いずれにせよALPとGGTは「胆汁の流れがスムーズか?」を見る指標であり、数値が高ければ胆管や胆嚢のチェック(超音波検査等)が勧められます。
肝臓の働き(役割)
肝臓は体内最大の臓器であり、生命維持に欠かせない重要な機能を多数担っています。主な肝臓の働きは大きく3つ(あるいは4つ)に分類できます:
栄養素の代謝・貯蔵: 食事から吸収されたタンパク質・脂質・糖質の分解や再合成を行い、身体に必要な物質(例えばアルブミンやコレステロールなど)を合成します。余分なブドウ糖はグリコーゲンという形で肝臓に蓄え、必要に応じてエネルギー源として放出します。ビタミンA・D・B12や鉄などのビタミン・ミネラルを貯蔵する役割もあります。
有害物質の解毒・分解: 肝臓は体内の解毒工場です。有害なアンモニアを尿素に変換したり、食品中の添加物や薬物、アルコールなど体にとって不要・有毒な物質を無毒化し、胆汁や尿中に排泄します。例えばタンパク質代謝で生じるアンモニアを尿素に変え排泄するのは肝臓の重要な役割です。
胆汁の生成・分泌: 肝臓では脂肪の消化吸収を助ける胆汁を絶えず生成しています。胆汁は胆嚢で濃縮・蓄えられ、食事の際に十二指腸へ分泌されて脂肪の消化を促進します。肝臓の病気で胆汁分泌が滞ると脂肪の消化不良や黄疸などの症状が出ます。
(その他:血液の凝固因子の合成、免疫物質の処理など) 肝臓は上述の3機能以外にも、血液を固めるための凝固因子を合成したり、古くなった赤血球の分解産物であるビリルビンを処理したり、免疫に関与する蛋白質を産生するなど多彩な役割を持っています。肝機能が高度に低下すると、低アルブミン血症(血液中のタンパク不足)や凝固異常(出血が止まりにくい)といった症状が現れるのは、これら肝臓の合成機能が損なわれるためです。
以上のように肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど普段は目立ちませんが、体の化学工場・解毒工場・倉庫としてフル稼働している極めて重要な臓器です。肝臓の働きが障害されると全身の様々な代謝に支障をきたすため、肝臓の健康維持は愛犬のQOL(生活の質)に直結します。
肝臓の数値が高い原因
前述のとおり、肝酵素値が高くなる原因は一つではありません。大きく分けると「原発性」と「二次性(反応性)」の2種類に分類できます。統計的には、犬の場合は原発性よりも二次性(肝臓以外の問題による反応性肝障害)の方が肝酵素上昇の原因として多いとも言われています。それぞれ具体的に見てみましょう。
原発性肝疾患(一次性)
「原発性」とは、その名の通り原因が肝臓そのものにある場合です。肝臓に直接起きた病気によって肝酵素が上昇しているケースで、代表的なものは以下で「原発性」とは、その名の通り原因が肝臓そのものにある場合です。肝臓に直接起きた病気によって肝酵素が上昇しているケースで、代表的なものは以下です。
慢性肝炎(特発性慢性肝炎): 犬で最も多い肝臓の病気です。原因を特定できない慢性的な肝臓の炎症で、長期間かけて徐々に肝細胞が破壊・線維化(瘢痕化)していきます。中高齢の犬によく発症し、初期は無症状だが血液検査でALT上昇が続く場合は要注意です。放置すれば肝硬変(末期状態)へ進行します。
急性肝炎・中毒性肝障害: 感染症(犬アデノウイルス1型による伝染性肝炎、レプトスピラ症など)や、薬物・毒物(人用の薬の誤飲、重金属、中毒植物など)、あるいは急な膵炎から波及する二次的な急性肝障害など。急性肝炎では数日以内に嘔吐・黄疸などの症状が出て、治療が遅れると命に関わります。
肝硬変: 慢性肝炎が末期まで進行し、肝臓が縮んで硬くなった状態です。肝不全症状(黄疸、腹水、神経症状、出血傾向など)が出る段階で、生存期間は大幅に短縮します。肝硬変そのものは不可逆的(元に戻らない)ため、いかにその手前で食い止めるかが重要です。
肝腫瘍: 肝臓の腫瘍には、肝細胞がんなど原発性の肝臓がんと、他のがんが肝臓に飛んだ転移性の腫瘍があります。いずれも肝酵素(特にALPやGGT)が上昇することがあります。肝細胞がんは外科手術で切除可能な場合、長期生存も期待できますが、転移性のものは原発巣のコントロールも含めた治療が必要です。
門脈シャント(先天性または後天性): 肝臓に入るべき血液がバイパスしてしまう血管奇形です。先天的に子犬で発見されることが多く、アンモニアの解毒ができないため神経症状(ふらつき、発作)が出ます。血液検査ではアンモニアや胆汁酸の上昇が顕著ですが、肝酵素も軽度上がることがあります。
上記の他にも、肝膿瘍(細菌感染による化膿)や胆管肝炎(胆管の炎症が肝実質に波及)など様々な肝臓の疾患が原発性に含まれます。これらの場合、治療のターゲットは肝臓そのものとなります。
2次性肝障害(反応性肝症)
「2次性」あるいは反応性肝障害とは、他の疾患に反応して肝臓の数値が上がっている状態を指します。肝臓自体に重大な病変がなくても、全身の病気に伴って肝酵素が漏出したり産生が増えたりすることがあります。犬ではこのタイプが非常に多く見られます。具体例を挙げましょう。
内分泌疾患: 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)では慢性的なコルチゾール過剰によりステロイド誘導性のALP上昇が起こります。甲状腺機能低下症でも代謝低下に伴い高コレステロール血症や肝酵素軽度上昇を伴うことがあります。糖尿病でも高脂血症から肝への脂肪蓄積や肝酵素上昇が見られることがあります。
心疾患・循環障害: 心不全などで肝臓への血流が慢性的に鬱滞するとうっ血肝となり肝酵素が上がります(ASTやALT)。また低酸素状態やショックでも一時的に肝細胞がダメージを受けALT上昇を来す場合があります。
感染症・炎症性疾患: 重度の歯周病や膵炎、重い皮膚病など、他臓器の感染・炎症が肝臓に負担をかけ肝酵素が反応性に上がることがあります。全身性の感染症(敗血症など)でも肝臓が影響を受けることがあります。
腫瘍の転移・悪性疾患: 他臓器のがんが肝臓に転移した場合や、白血病・リンパ腫など血液のがんで肝臓が浸潤される場合も肝酵素上昇が見られます。特にリンパ腫では肝臓・脾臓がしばしば侵されALT/ALPが上がります。
薬剤・サプリメントの影響: 長期投与している薬がある場合、それが原因で一時的な肝酵素上昇が起きることがあります。例えばフェノバルビタール(てんかん治療薬)はALT・ALPを慢性的に高めますし、ステロイドも前述の通りALP上昇を招きます。ある報告では、原因不明の肝酵素上昇があった犬で、与えていたサプリメントを中止したら正常化したケースもあるとのことです。過剰なハーブや漢方サプリにも注意が必要です。
以上のように、肝臓以外の様々な病態で「肝臓の数値」は影響を受けます。この場合、まずは根本原因の治療(心不全の治療、ホルモン病の管理など)が優先され、肝臓そのものへの治療は補助的になります。反応性肝障害の場合は、原因が解決すれば肝酵素も正常化することが多いです。
まとめポイント: 愛犬の肝酵素が高いと言われたら、上記の原発性肝疾患なのか二次性の影響なのかを見極める必要があります。獣医師は血液検査の他にエコー検査や追加の血液項目(胆汁酸検査など)を組み合わせ、総合的に診断します。何も症状が無くても数値だけ高い場合、一時的な変動の可能性もあるため一定期間後に再検査を行い経過を見ることもあります。
肝臓病の初期症状と末期症状
肝臓は予備能が高く再生能力も強いため、障害を受けても初期には症状が出にくい臓器です。そのため「沈黙の臓器」と呼ばれ、健康診断で偶然見つかるまで飼い主さんが気づかないケースも多いのです。しかし病気が進行して肝機能が大きく低下すると、様々な症状が現れてきます。ここでは初期に見られる可能性がある症状と、末期(重度進行時)の症状を分けて説明します。
<初期症状(出ない場合も多い)> 初期の肝障害では全く無症状のことが少なくありません。肝臓はかなりの部分がダメージを受けてからでないと症状に現れないためです。それでも次のような兆候が見られる場合があります:
元気消失・疲れやすい: なんとなく散歩を嫌がる、遊びたがらない、以前より寝てばかりいる等。肝機能低下で代謝が落ちるとスタミナ切れを起こしやすくなります。
食欲不振・体重減少: 好物にも見向きしない、食べる量が減った、痩せてきた(筋肉が落ちてきた)など。肝臓は食欲にも関与する臓器で、異常があると食欲減退を招くことがあります。
嘔吐・下痢: ときどき吐く、軟便・下痢をする。消化不良気味になるため慢性的な消化器症状が出る場合があります。血便が出ることもあります(タール様の黒い便=メレナは消化管出血のサイン)。
多飲多尿: 水を飲む量と尿の量が増える。肝疾患ではホルモンの失調により尿が増えやすくなることがあります(※ただし多飲多尿は腎臓病や糖尿病など他の病気の症状でもあるため、単独では手掛かりとして弱いです)。
これら初期症状は出ないことも多く、出ても非特異的(他の病気でも起こりうる)です。そのため見逃されがちですが、「シニア犬でなんとなく元気・食欲が落ちてきた」という場合には肝臓を含む内臓の検査を考慮しても良いでしょう。非特異的(他の病気でも起こりうる)です。そのため見逃されがちですが、「シニア犬でなんとなく元気・食欲が落ちてきた」という場合には肝臓を含む内臓の検査を考慮しても良いでしょう。
<末期症状(肝不全の症状)> 肝臓病が末期段階まで進行すると、明らかな異常が次々と現れます。代表的なものは:
黄疸(おうだん): 白目や歯茎、皮膚が黄色くなる症状です。肝臓で処理しきれないビリルビン(黄色い胆汁色素)が体に蓄積するために起こります。肉眼で黄疸が見えるのは重度のサインです。
腹水: お腹に液体がたまる症状です。低アルブミン血症や門脈圧亢進により、腹腔内に漏出液が溜まります。お腹が膨れ、進行すると呼吸困難の原因にもなります。
神経症状(肝性脳症): フラフラとふらつく、壁に頭を押し付けるような行動、徘徊、ひどい場合は痙攣発作や昏睡など。肝臓で解毒できないアンモニアなどが脳に作用し、中枢神経症状を引き起こす状態です。
出血傾向: ちょっとした打撲で内出血したり、鼻血が出たり、歯茎からの出血が止まりにくくなったりします。肝臓の凝固因子合成能低下やビタミンK不足により血が固まりにくくなるためです。
重度の食欲廃絶・衰弱: 全く食べられない、水も飲まない、横になったまま起き上がれない、といった衰弱状態に陥ります。
末期症状まで進行した肝臓病は予後不良とされ、残念ながら長期生存は難しいケースが多いです。例えばある研究では、犬の慢性肝炎の平均生存期間は約561日(約1年6か月)でしたが、肝硬変と診断された犬では平均わずか23日しか生存できなかったと報告されています。特に腹水を伴うケースでは平均生存22.5日と極めて短く、高ビリルビン血症(ひどい黄疸)や凝固異常、低アルブミン血症がある場合は予後が悪い因子とされています。もちろん個体差や治療介入にも左右されますが、末期症状が出ている段階での完治は難しいのが現実です。だからこそ、沈黙の臓器である肝臓の病気は早期発見・早期治療が何より重要なのです。
飼い主さんへのアドバイス: 黄疸や神経症状など明らかな異常が見られたら、迷わず一刻も早く動物病院へ連れて行ってください。末期症状が出ている場合、集中的な治療で延命やQOL改善を図りますが、治療反応が悪ければ余命は数週間~数ヶ月と考えざるを得ません。そうなる前に定期健診を受け、肝酵素の変化や軽微な症状を見逃さないことが大切です。
肝臓の治療方法
肝臓病の治療は、その原因や進行度によって異なります。一次性の慢性肝炎であれば内科療法(薬物と食事)で長期コントロールを目指しますし、腫瘍であれば外科手術が検討されます。ここでは、犬の慢性肝炎などで一般的に用いられる薬物療法とサポート療法について説明します(※治療法は獣医師の判断で決定されますので、以下は代表的な例です)。
ステロイド(免疫抑制剤)
慢性肝炎の治療の第一選択としてよく用いられるのがコルチコステロイド(副腎皮質ステロイド)です。代表薬はプレドニゾロンで、抗炎症作用と免疫調整作用によって肝臓内の過剰な炎症反応を抑えます。特に原因不明の慢性肝炎(特発性慢性肝炎)では、肝臓へのリンパ球浸潤など免疫介在的な炎症が主と考えられるため、ステロイドで炎症を沈静化させることが治療の柱となります。
投与量と期間: 初期には1~2 mg/kg/日程度の比較的高用量から開始し、2~4週間程度かけて肝酵素値や症状の改善を図ります。その後、効果が確認できたら徐々に減量していき、最終的には隔日投与(1日おき)などの低用量維持療法に移行します。これはステロイドの副作用を軽減するためで、漫然と高用量を続けると糖尿病や筋力低下、易感染など様々な副作用リスクがあるためです。
効果と注意点: 多くの場合、ステロイド開始後にALTやASTが徐々に低下し、犬の元気・食欲も改善してきます。ただし、全ての慢性肝炎がステロイドに反応するわけではない点に注意が必要です。例えば銅蓄積が主因の肝炎では、まず銅の除去治療が優先されますし、末期に近い肝硬変状態ではステロイドの効果も限定的です。また、ステロイド自体が肝酵素(ALP)を上昇させる作用があるため、治療経過の評価にはALTやASTなど他の指標も含めて判断します。
ウルソ(ウルソデオキシコール酸)
ウルソとは、人医療でもおなじみのウルソデオキシコール酸(UDCA)製剤です。熊胆由来の成分で、肝臓内の胆汁フローを改善する作用があります。胆汁うっ滞の改善や胆汁酸の組成改善によって肝細胞を保護し、さらに免疫調節作用や抗炎症作用も持つとされています。
投与対象: ウルソは胆汁うっ滞を伴う肝疾患(例えば慢性活動性肝炎に伴う胆管炎、胆泥症を併発しているケースなど)でよく使われます。GPTやALPが高く、エコー検査で胆嚢に泥状の胆汁が溜まっているような場合に処方されることが多いです。また、高ビリルビン血症(黄疸)があるときにも胆汁排泄を促す目的で使われます。
作用とエビデンス: UDCAは元々肝臓に存在する胆汁酸の一種で、「毒性の強い内因性胆汁酸」を「毒性の弱いUDCA」に置き換えることで肝細胞膜の安定化を図ります。また胆汁の分泌自体を増やし、うっ滞を解消します。さらに抗炎症・抗アポトーシス作用により肝細胞の生存を助けると考えられています。ただし獣医領域でのエビデンスは必ずしも多くなく、「ウルソやSAMe、ビタミンEなど肝保護剤の有効性を裏付ける強固な根拠は多くないが、日常的に補助療法として使用されている」のが現状です。安全性は高い薬ですので、補助的に投与されるケースが多いと言えます。
肝臓保護のサプリメント
動物用サプリメントにも肝臓に良いとされる成分を含むものが多数あります。「サプリメントだけで肝臓病が治る」ものではありませんが、肝細胞の保護や肝機能サポートを目的に、処方薬と併用されることがあります。主な有効成分と期待される作用は以下のとおりです。
SAMe(S-アデノシルメチオニン): 肝臓で生成される物質で、グルタチオンという強力な抗酸化物質の産生を促進します。市販の肝臓サプリに配合され、抗酸化による肝細胞保護作用や、胆汁うっ滞改善作用が期待できます。
ビタミンE: 抗酸化ビタミンの代表で、肝臓で発生する過酸化脂質の除去を助けます。慢性肝炎の犬では血中ビタミンE濃度が低下しやすいとの報告もあり、補給が推奨される場合があります。
シリマリン(ミルクシスル抽出物): ハーブであるマリアアザミ由来の成分で、古くから「肝臓に良いハーブ」として利用されてきました。抗酸化作用・抗炎症作用に加え、肝細胞膜を保護しタンパク質合成を促進して肝細胞の再生を助ける効果が報告されています。ヨーロッパでは人の肝炎治療にも使われる成分です。
タウリン・オルニチン: アミノ酸の一種で、解毒サイクルの促進や肝細胞浸潤の抑制を目的に配合されます。タウリンは胆汁酸の排泄を促す作用もあります。
グリチルリチン酸(カンゾウ由来): 肝機能改善作用があるとされ、人の慢性肝炎でも用いられる成分です。抗炎症・抗線維化作用が期待されます。
これらの成分を含む動物用サプリメント(市販品)を、獣医師の指導のもと薬物治療の補助として与えることがあります。ただし繰り返しになりますが、現段階でこれらサプリメントのみで劇的に肝炎が治るという科学的証拠は十分でないことは留意してください。あくまで「肝臓の負担を軽くし、治療をサポートする」目的で、用法用量を守って使用することが大切です。。
食事療法:肝臓に良い食べ物・悪い食べ物
肝臓病の管理において、食事療法は非常に重要な柱です。肝臓に負担をかける栄養素を制限し、逆に肝機能を助ける栄養を適切に補うことで、病状の進行を遅らせたり症状を緩和する効果が期待できます。ここでは肝臓に良いとされる食材と、避けるべき食材・注意点について具体的に解説します。
肝臓に良い食べ物の例
肝臓に良い食事とは、一言で言えば「肝臓への負担が少なく、必要な栄養素はしっかり摂れる食事」です。肝臓病用の療法食も市販されていますが、手作りで食材を工夫する場合やトッピングを加える場合、以下のような食材が推奨されます。
高消化性の良質なたんぱく質: 肝臓病では過剰なたんぱく質はアンモニア蓄積のもとになりますが、不足しすぎても筋肉が落ち抵抗力が低下します。ポイントは量を調整しつつ質の良いタンパク質を与えることです。具体的には脂肪分の少ない肉や白身魚、卵白など消化の良い動物性たんぱくや、乳製品・大豆製品などを活用します。特に植物性(大豆)や乳由来のタンパク質は、動物性タンパク質に比べてアンモニアの発生量が少ないとされています。例として豆腐、納豆、カッテージチーズ、プレーンヨーグルトなどは少量ずつ肝臓病の子のタンパク源として利用できます。納豆はタンパク質に富み消化吸収も良く、ビタミンB群が肝臓の代謝を助けるのでおすすめですが、付属のタレは塩分が多いので使わず、ひきわり納豆をティースプーン1杯程度トッピングするくらいが適量です。
適度な炭水化物: 肝臓の慢性疾患では、低血糖を起こしにくくするためエネルギー源としての炭水化物も重要です。ただし精製された糖質(白米や白パン)は急激に血糖値を上げるので大量には向きません。与えるなら食物繊維を含む複合炭水化物が望ましく、例えば玄米やサツマイモ、カボチャ、オートミールなどを少量ずつ使うと良いでしょう。玄米は白米より食物繊維が多く消化を緩やかにし、満腹感も得られやすい利点があります(ただし玄米の糠部分に健康を害する成分が含まれることもあるため、「ロウカット玄米」のように加工されたものが安全です)。
ビタミン・ミネラル類(抗酸化栄養素): 肝臓での解毒作業を助け、損傷を防ぐために抗酸化ビタミン(ビタミンA・C・E)や亜鉛、セレンなども十分に摂りたい栄養素です。これらは新鮮な緑黄色野菜や果物、魚介類に含まれます。例えばニンジンやカボチャはビタミンA源、リンゴやキウイはビタミンC源、カキ(牡蠣)は亜鉛源です。またブロッコリースプラウトなどはグルタチオン産生を高めるスルフォラファンを含み、抗酸化作用が期待できます。野菜類は犬にとって消化しにくいので加熱してペースト状にして与えると良いでしょう(食物繊維も摂れますが、与えすぎは下痢の原因になるため全体の20%以内程度に)。
BCAA(分岐鎖アミノ酸): バリン・ロイシン・イソロイシンの3種のアミノ酸は筋肉で代謝され肝臓に負担をかけにくいため、肝疾患時に不足しやすく補給が推奨されます。BCAAはマグロ赤身、カツオ、鶏むね肉などに豊富です。市販の療法食ではBCAA強化されているものもあります。
ハーブ類・機能性食品: 前述のシリマリン(ミルクシスル)はサプリの他にハーブティー等でも摂取できます。またウコン(ターメリック)はクルクミンという成分に肝機能向上効果や胆汁分泌促進効果があり、犬用サプリでも利用されています。ただしウコンそのものは苦味が強く大量投与は難しいため、サプリで与えるほうが現実的でしょう。その他、ゴマ(セサミン)も抗酸化作用で肝臓を守る効果が期待できます。犬にはすり潰したすりゴマを少量ふりかけると良いですが、与えすぎは下痢に注意です。
野菜類の例: キャベツは食物繊維が豊富で胃腸の調子を整え、ビタミンCやU、抗酸化成分(フラボノイド等)も含みます。さらにキャベツには肝臓内の余分な脂肪を除去し肝機能を高める作用があるとされ、肝機能が低下している愛犬に与えたい野菜の一つです。パセリもβカロテンなど抗酸化成分が含まれ、肝臓の炎症による組織障害を抑える効果が期待できます。刻んで食事にトッピングする程度で十分です。
以上のような食材を組み合わせ、低脂肪・適切なたんぱく質量・高ビタミンのバランスを目指すのが理想です。具体的な手作りメニューについては、肝臓の状態によって異なるため詳述しませんが、基本は「市販の肝臓病用療法食」をベースに、不足しがちな栄養を上記の安全な食材で補う形が現実的です。療法食以外のご飯を与えて良い段階かどうかは獣医師と相談してください。
肝臓に悪い食べ物・注意すべき食事
反対に、肝臓の数値が高い犬に与えない方がよい食べ物も把握しておきましょう。肝臓に悪影響を与える、もしくは肝臓の負担になるリスクが高いものとして以下が挙げられます。
高銅の食品: 銅は生体に必須の微量元素ですが、過剰に蓄積すると肝細胞を傷害します。特に遺伝的に銅代謝に問題がある犬種(ベドリントン・テリア、ラブラドールなど)では銅の摂取制限が極めて重要です。銅を多く含む食材の代表はレバー(肝臓)や赤身肉、貝類、納豆、さつまいもなどです。人間では「肝臓に良いから」とレバーを食べる民間療法がありますが、犬の場合は逆効果になり得るので注意してください。肝臓病の犬には牛や鶏のレバーは与えない、おやつのジャーキー類も肝臓や腎臓を使用しているものは避けるなど工夫が必要です。
高脂肪の食品: 脂肪分の多い食事は肝臓に中性脂肪が蓄積しやすく、脂肪肝を助長します。また胆汁うっ滞がある場合、脂肪を消化できず下痢や嘔吐の原因にもなります。具体的にはバターや生クリーム、揚げ物の衣、脂身の多い肉(霜降り肉、皮つき鶏肉など)は避けましょう。調理の際も油は極力使わず、茹でる・蒸す調理が適しています。市販のおやつではチーズやサラミなど高脂肪なものはNGです。肝臓に負担をかけずカロリー補給するには、植物油よりも炭水化物の方がまだ安全です(※ただし糖尿病等が無い場合)。
糖分・でんぷんの過剰: 上で述べたように、適度な炭水化物は必要ですが白米や小麦粉など精製穀物の過剰は避けます。これらは血糖を急上昇させ、二次的に高脂血症や脂肪肝を招きやすいためです。特に肝臓が悪い子は並行して糖代謝や脂質代謝が乱れていることも多く、高糖質食は病態を悪化させかねません。ご飯を与える場合は玄米にする、少量にするなど工夫しましょう。またお砂糖たっぷりの人間のお菓子(ケーキ、クッキー等)は論外です。肝臓に負担なだけでなく肥満にも繋がります。
食品添加物・保存料: 人工的な添加物は肝臓にとって異物であり、解毒する際に酵素を浪費します。例えば人工着色料や保存料が多く含まれる加工食品(ハム、ソーセージ、スナック菓子等)は避けるべきです。市販ドッグフードでも、無添加で消化の良い原材料を使ったものを選ぶのが望ましいでしょう。
塩分(ナトリウム)過多: 肝硬変で腹水がある場合などは、塩分制限も必要です。ナトリウムを摂りすぎると体内に水分が貯留しやすくなるため、腹水や浮腫を悪化させます。肝臓病の子には味付けは極力薄くし、人の食べ物(醤油味や味噌味のもの)をおすそ分けしないようにしてください。
その他避けるべきもの: 玉ねぎやニンニク、長ネギなどのネギ類はご存知の通り犬に有害で、溶血性貧血を引き起こします。キシリトール(人工甘味料)も低血糖から急性肝不全を起こす猛毒です。アルコールも犬には厳禁です。これらは肝酵素を急上昇させるどころか命に関わる中毒症状を引き起こします。肝臓に良い悪い以前の問題ですが、誤食しないよう注意しましょう。
最後に、手作り食についての注意です。肝臓病でも手作りは可能なものの、栄養バランスの計算が非常に難しい側面があります。特に慢性肝炎ではたんぱく質量の微調整やビタミン・ミネラルの管理が必要で、独自の判断での手作りはリスクもあります。獣医師やペット栄養管理士に相談しながら進めるか、基本は市販の療法食に頼った方が無難です。市販療法食は肝臓に配慮して高品質タンパク質を必要最低限含み、銅やナトリウムを制限し、亜鉛などを強化して作られています。その上で、「愛犬がなかなか食べてくれない」といった場合に限り、上記の安全な食材でトッピングしたり嗜好性を高める工夫をしましょう。肝臓病では食べないことが何より悪影響(低血糖や筋肉消耗を招く)なので、食欲維持も重要なケアです。
まとめ
肝臓の数値が高いと告げられると飼い主としては不安になりますが、まずは冷静に原因の特定と適切な対処を行うことが大切です。肝酵素上昇の背景には、肝臓そのものの慢性炎症から他の病気による反応性の変化まで様々な可能性があります。獣医師と相談しながら追加検査を行い、愛犬の状態に合った治療計画を立てましょう。
「沈黙の臓器」である肝臓は、症状が出たときにはすでに進行していることが少なくありません。しかし幸い、肝臓は再生能力の高い臓器でもあり、早期に適切な治療・食事管理を開始すれば数年間健康に過ごせる可能性も十分あります。実際、初期~中期の慢性肝炎であれば、ステロイド治療や食事療法の組み合わせで多くの症例が良好な経過をたどったとの報告もあります。
日常生活では、肝臓に優しい食事と定期的なモニタリングが肝要です。さつまいもをはじめとする肝臓に良い食材を上手に取り入れつつ、塩分や脂肪分を抑えた食事で肝臓の負担を減らしてあげましょう。
さらに半年~一年ごとの血液検査や超音波検査で肝臓の状態をチェックし、数値の変化に早めに気づくことも大切です。
愛犬の肝臓を守れるのは飼い主さんと獣医師です。 飼い主さんは「飼い主ファースト」の精神で、愛犬の様子を日々観察し最適なケアを選んであげてください。肝臓の数値が高めと言われたからと過度に怯える必要はありませんが、くれぐれも放置はせず、エビデンスに基づいた対策で愛犬の健康寿命を延ばしてあげましょう。
(監修:獣医師・ペット栄養管理士)
【参考文献】
- ACVIM (米国獣医内科学会)コンセンサスステートメント抄訳 「犬の慢性肝炎の診断・治療指針」 (2019)vth-tottori-u.jp
