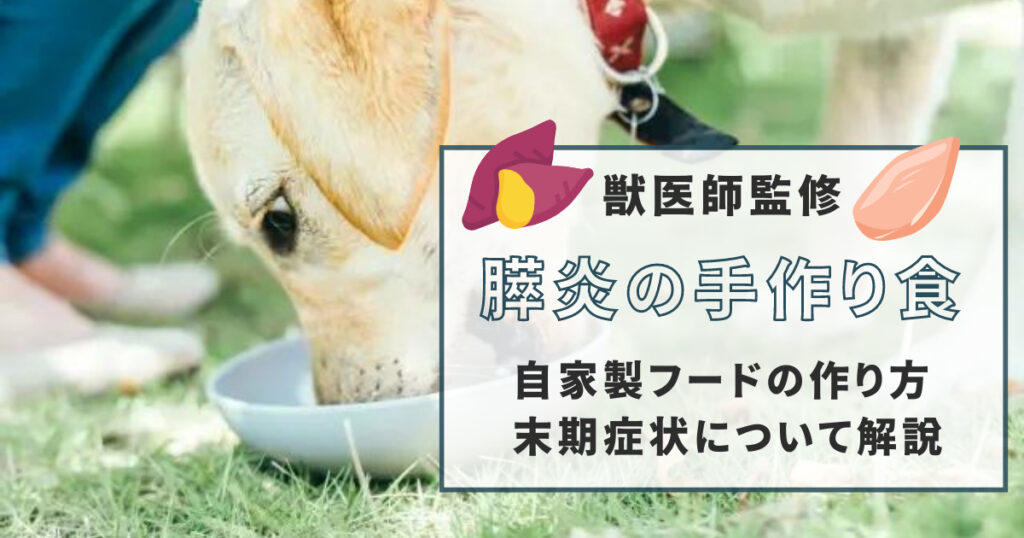
愛犬が膵炎と診断され、食事内容に悩んでいませんか? 獣医師監修の本記事で犬の膵炎における手作り食のポイントを解説します。ささみやさつまいもを使った低脂肪の自家製フードの作り方から、膵炎の末期症状まで最新の知見にもとづき詳しく説明します。
膵炎かも?まず確認したい愛犬の症状
- 愛犬が突然何度も吐いてしまう
- 食欲がなく、元気もなくぐったりしている
- お腹を床につけお尻を高く上げる「祈りのポーズ」をする
- 膵炎と診断されたが、どんな食事を与えればよいかわからない
こうした症状やお悩みに心当たりはありませんか?これらは犬の急性膵炎で見られる典型的な症状かもしれません。
膵炎は高齢犬や肥満の犬で起こりやすい消化器の病気ですが、実際には原因不明の「特発性」が大半を占め、若い犬でも発症し得ます。重症化するとショックや多臓器不全を引き起こし、**急性膵炎の死亡率は27~58%**にも及ぶと報告されています。そのため、できるだけ早期に治療を開始しなければ命に関わる非常に怖い病気です。
治療にはいくつものアプローチが必要ですが、特に重要なのが**食事療法(低脂肪食)と点滴療法(脱水補正)**です。
膵炎の食事管理でまず思い浮かぶ食材といえば「ささみ」でしょう。ささみは脂肪分が少なく高たんぱくなため、膵炎など消化器疾患のある犬に適した食材です。また、同じく低脂肪の食材として馬肉や鹿肉もよく利用されます。しかしタンパク源だけでは栄養が偏るため、ビタミンや食物繊維を豊富に含むさつまいもなどのイモ類を加熱調理して組み合わせるとよいでしょう。
では、実際にささみやさつまいもは膵炎の愛犬に与えても問題ないのか?また、それらを使った手作り療法食はどのように作り、どれくらいの量を与えれば良いのでしょうか?
本記事では、獣医師およびペット栄養管理士の観点から犬の膵炎に対する手作り食について、レシピや適切な給餌量、さらに膵炎の初期症状から末期症状までを詳しく解説します。愛犬が膵炎と闘っている飼い主さんにとって、きっとお役に立つ内容です。
膵臓とはどんな臓器?
まず膵炎の解説に入る前に、「膵臓(すいぞう)」という臓器の役割を簡単におさらいしましょう。
膵臓はお腹の中にある消化器官の一つで、内分泌と外分泌という2つの重要な働きを担っています。内分泌とはホルモンを血液中に分泌する働きで、膵臓からは血糖値を調節するインスリンや、血糖値を上げるグルカゴン、さらにソマトスタチンなどのホルモンが分泌されます。インスリンは血糖値を下げ一定に保つ役割を果たしています。
一方、外分泌として膵臓は、食物の消化に必要な様々な消化酵素を含む「膵液(すいえき)」を産生し、膵管を通じて十二指腸(小腸の最初の部分)に分泌します。膵液にはリパーゼ(脂肪を分解)、アミラーゼ(デンプンを分解)、トリプシン(タンパク質を分解)といった酵素が含まれ、胃から送られてきた食べ物を小腸で消化吸収するのを助けます。また膵液はアルカリ性で、胃酸で酸性になった内容物を中和する働きも持っています。
このように生きていく上で欠かせない栄養素の消化に関わる膵臓ですが、ここに炎症が生じてしまうのが「膵炎」です。それでは次に膵炎とはどんな病気かを見ていきましょう。
膵炎とはどんな病気?
膵炎(すいえん)とは、その名の通り膵臓に炎症が起こる病気です。
膵臓では前述の通りトリプシンなどの消化酵素が作られますが、本来は膵臓から分泌された後に初めて活性化して働きます。しかし何らかの原因でこれらの消化酵素が膵臓内で活性化されてしまうと、酵素が膵臓自身を自己消化し、膵臓の組織が破壊されて激しい炎症を引き起こします。炎症が膵臓周辺から全身に波及すると嘔吐・下痢・腹痛・腰痛など様々な症状をもたらし、重症の場合は腹膜炎や多臓器不全など致命的な合併症に発展します。
膵炎には急性膵炎と慢性膵炎の2種類があります。急性膵炎は今説明した通り突然発症して進行も速いのが特徴で、短期間で重篤化することがあります。一方慢性膵炎は、急性膵炎を繰り返すうちに膵臓の組織が徐々に線維化・硬化して萎縮し、膵酵素の分泌能力が落ちていく状態です。慢性膵炎では症状は急性ほど激しくはありませんが、じわじわと膵臓が機能不全に陥っていきます。また膵炎の影響で膵臓に負担がかかり続けると、糖尿病を併発するリスクも高まることが知られています。
命に関わるケースもある
重度の急性膵炎に陥ると、炎症によって急性腎障害(急性腎不全)などの多臓器不全を起こし、命にかかわる危険性があります。症状が軽いうちに適切な治療を開始することが何より重要です。
膵炎の主な原因・危険因子
膵炎はある日突然起こることが多いですが、発症に関連すると考えられている原因や危険因子がいくつか知られています。代表的なものは次の通りです。
- 肥満(太りすぎの犬は膵炎リスクが高い)
- 過食(一度に大量に食べると膵臓に負担)
- 高脂肪食の摂取(脂肪分の多いドッグフードやおやつ、人間の食べ物の盗み食い)
- ストレス(強いストレスが引き金になるケースも)
- ゴミ漁り(生ゴミや腐敗したものを食べると膵炎を起こすことがある)
- 特定の薬剤(フェノバルビタール、L-アスパラギナーゼ、アザチオプリン、利尿剤などの投与歴)
- 外傷や事故(高所からの落下などで膵臓が損傷)
- 他の病気(膵炎を引き起こしうる基礎疾患:高脂血症、甲状腺機能低下症、クッシング症候群、副腎皮質機能亢進症、糖尿病、胆石症、肝炎、腎不全など)
- 蜂など虫刺され(蜂毒が膵炎を誘発した報告もあり)
特に脂肪分の多いものを日常的に食べている犬は要注意です。高脂肪のドッグフードだけでなく、人間の食べ物は犬にとって脂質過多である場合が多いため、日頃から人の食べ物を与えられている犬は膵炎のリスクが高まります。また添加物の多い低品質なフードやおやつを常用していることが原因ではないかという意見もあります。
さらに上記の通り膵炎を起こしやすくなる病気(基礎疾患)も多数存在します。しかし実際の臨床現場では、膵炎の明確な原因を突き止められないことが非常に多いのも事実です。このような場合は特発性膵炎と呼ばれます。ある報告では、膵炎と診断された犬の90%以上で原因を特定できなかったとも言われています。
膵炎の症状:初期症状と末期症状
膵炎の症状は急性か慢性か、重症度によって大きく異なります。一般に急性膵炎では強い炎症による激しい症状が現れ、適切な治療が遅れるとショック症状や多臓器不全に至り死亡することもあります。一方で慢性膵炎は急性膵炎が長期化・反復することで慢性経過となった状態で、症状は緩徐で軽度ですが、じわじわと膵臓が破壊され機能低下が進みます。
膵炎の初期症状(急性膵炎)
急性膵炎では初期段階から、以下のような激しい消化器症状が見られます。
- 激しい腹痛(お腹に強い痛みがある)
- 頻繁な嘔吐(何度も吐く)
- 下痢・血便(消化管粘膜の出血も伴うことがある)
- 多量のよだれ(吐き気が続くため唾液過多になる)
- 食欲不振(気持ち悪さと痛みで食べなくなる)
- 発熱(炎症により高熱が出る場合も)
- 脱水(嘔吐や下痢で水分が失われる)
- 元気がない(ぐったりして反応が鈍い)
- 呼吸が浅く速くなる(痛みやショックによる)
- 腰や腹部の痛み(お腹や腰の触診を嫌がる)
このように、膵炎では早期から嘔吐・下痢といった消化器症状が目立ちます。また常に吐き気がある状態のため、犬はヨダレを垂らし続けることも多いです。
膵炎の末期症状(重症例)
膵炎が進行し重症化すると、末期的な症状が現れます。具体的には以下のような状態です。
- 低体温(ショック状態に陥り体温が下がる)
- 腹膜炎(膵臓から腹腔全体に炎症が広がる)
- 腹水(お腹に体液がたまる)
- 血栓症(体内で血の塊ができ、血管を詰まらせる)
- 黄疸(胆管炎症や肝障害で皮膚や白目が黄色くなる)
- 点状出血(全身の凝固異常により皮膚や粘膜に小さな出血斑が出る)
- 呼吸困難(胸水や全身衰弱により呼吸が苦しくなる)
- 多臓器不全(腎不全、肝不全など複数の臓器が機能停止)
中でも血栓塞栓症とは、膵炎の炎症で血液が固まりやすくなり血管内に血栓(血の塊)ができてしまう状態です。血栓が肺や門脈などに詰まると臓器が壊死し、致死的な多臓器不全を引き起こします。また重症膵炎では強い炎症により全身の血液循環が破綻し、**DIC(播種性血管内凝固)**という凝固障害やショックに陥って死亡率が非常に高くなります。
「祈りのポーズ」は腹痛のサイン
お腹を痛めた犬がよく見せる姿勢に祈りのポーズがあります。前肢と上半身を地面に伏せつつお尻だけを高く突き上げた独特の格好で、一見まるでお辞儀や祈っているようにも見える姿勢です。急性膵炎では強い腹痛のため、犬は背中を丸めてお腹を守ろうとしたり、お尻を上げて胸を床につける祈りの姿勢をとることがあります。これはお腹を圧迫すると激痛が走るため、少しでもお腹への負荷を減らそうとする自己防衛の姿勢なのです。
膵炎を起こしやすい犬種
どの犬でも膵炎になる可能性はありますが、特に膵炎を起こしやすいとされる犬種が知られています。代表的な膵炎の好発犬種は次の通りです。
- ミニチュア・シュナウザー(遺伝的に高脂血症を起こしやすく、膵炎のリスクが高い)
- ヨークシャー・テリア(小型で脂質代謝が弱く、高脂肪食で膵炎になりやすい)
- イングリッシュ・コッカー・スパニエル(免疫介在性の疾患を起こしやすく、膵炎につながることがある)
- コリー(遺伝的要因で膵炎の報告あり)
- ボクサー(同上)
- シェットランド・シープドッグ(同上)
- ウェスト・ハイランド・ホワイト・テリア(ウェスティ)(同上)
特にミニチュア・シュナウザーは遺伝的に脂質の代謝異常を抱えやすい犬種で、血中の中性脂肪が高くなりがちなため膵炎の発症率が高いとされています。また前述のコッカー・スパニエルも自己免疫疾患の好発犬種で膵炎との関連が指摘されています。
もちろん上記に挙げた犬種以外でも、すべての犬に膵炎発症のリスクがあります。日々の食事管理と体調チェックが何より大切です。
膵炎の診断方法
膵炎は一つの検査だけでは断定が難しく、総合的な検査所見から診断します。特に急性膵炎では血液検査で炎症の指標(白血球数やCRP値)の著しい上昇が見られますが、それだけで膵炎と即断はできません。一般的に以下のような検査・所見を総合して診断が行われます。
- 血中膵特異的リパーゼ検査(cPL):スナップテストや外注の定量検査で膵炎マーカーであるリパーゼ値を測定し、陽性や高値であれば膵炎が疑われます。
- 一般血液検査:白血球の増多やCRP高値など強い炎症反応が出ている。
- 腹部超音波検査:膵臓の形態異常(腫大や浮腫)や周囲脂肪組織の高エコー像(炎症により輝いて見える)を確認。腹水の有無もチェック。
- X線検査:腸閉塞や誤飲・腫瘍など他の病態が無いか確認(膵炎が疑われる所見としては腹部X線で十二指腸の位置異常などが見られる場合もあります)。
膵炎かどうかを診断する上で特に有用なのが膵特異的リパーゼという膵臓由来の消化酵素の測定です。犬の急性膵炎ではこのリパーゼが異常高値を示すことが多く、スクリーニング検査として用いられます。ただし注意すべきは、リパーゼの値が高くても必ずしも膵炎とは限らないことです。たとえば以下のような病気でもリパーゼが上昇する場合があります。
- 腹膜炎
- 胃腸炎
- 胃捻転・拡張
- 消化管の異物閉塞
- 肝炎・胆嚢炎
- 心疾患
- 糖尿病
- クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)
- 肥満
このように他疾患でもリパーゼが高くなることがあるため、リパーゼ検査結果だけで決めつけず画像検査などで他の病気を除外することが重要です。超音波検査では犬の膵臓が通常5~8mm程度の厚さですが、膵炎になると1.3~1.5cm以上に腫れて白くぼやけて見えたり、周囲に腹水が溜まるケースもあります。ただし似たような所見は腸閉塞や腫瘍でも起こり得るため、総合的な判断が必要です。
膵炎の治療法【内科療法と食事療法】
膵炎と診断された場合、入院の上で集中的な内科治療が行われるのが一般的です。具体的には、以下のような治療を組み合わせて症状の改善と膵臓の保護に努めます。
- 制吐剤の投与(吐き気止め)
- 制酸薬の投与(胃酸の分泌を抑える)
- 静脈点滴(輸液による脱水の是正と循環維持)
- 鎮痛剤の投与(痛みのコントロール)
- 早期の経口摂食(低脂肪の消化の良い食事を早めに与える)
- 副腎皮質ステロイドの投与(炎症を抑える効果を期待、必要に応じて)
- 膵炎治療薬の投与(フザプラジブナトリウム水和物=商品名ブレンダZなど)
制吐剤(吐き気止め)
膵炎では頻回の嘔吐により重度の吐き気と脱水が生じているケースがほとんどです。嘔吐が続くと食事も水も摂れず体力が奪われるため、初期治療では制吐剤による嘔吐コントロールが重要となります。代表的な犬の制吐薬は**マロピタント(商品名セレニア)**で、これはNK1受容体拮抗薬といって脳の嘔吐中枢および末梢の両方に作用し強力に吐き気を止めてくれます。
制酸薬(胃酸を抑える薬)
膵炎を発症すると副交感神経の刺激などで胃酸過多に陥ることがあります。胃酸が出過ぎると胃や腸の粘膜が荒れて胃潰瘍や腸炎を起こし、さらに食欲が低下して悪循環に陥ります。そのため胃酸を抑える制酸薬も用いられます。一般的には**プロトンポンプ阻害薬(オメプラゾール、ランサプラゾール等)やH2ブロッカー(ファモチジン等)**が使われ、胃腸粘膜を保護します。
静脈点滴(輸液療法)
膵炎の犬は重度の脱水状態になっていることが多いです。嘔吐・下痢で水分が奪われる上、炎症が広がることで血管内から水分が漏れ出し、血液が濃縮され循環血液量が減少してしまうからです。そのため、膵炎で来院した犬には静脈点滴による集中的な補液が行われます。皮下点滴では追いつかない重度の脱水では、数日間にわたり持続点滴が必要になるケースも珍しくありません。
疼痛管理(痛みを和らげる)
前述の通り急性膵炎では激しい腹痛があるため、鎮痛も治療の重要な柱です。犬の鎮痛にはオピオイド系鎮痛剤(麻薬系鎮痛薬)が効果的で、ブプレノルフィンやフェンタニルといった薬剤が用いられます。必要に応じてこれらを持続点滴で投与し、痛みを和らげてあげます。
早期の経口給餌(低脂肪食の導入)
かつては膵炎の治療=「絶食」というのが定番でした。膵臓を休めるために1~2日何も与えない、という方法です。しかし近年、犬猫の膵炎治療ではできるだけ早期に栄養を与えることが推奨されるようになってきました。絶食が長引くと腸粘膜のバリア機能が落ち、かえって状態が悪化する可能性が指摘されているためです。そのため現在では、吐き気が治まったら可能な限り早く低脂肪の消化の良い食事を少量ずつ与えるのが一般的です(自力で食べない場合はシリンジでの強制給餌や、長期なら経鼻・経食道チューブ給餌も検討します)。
もちろん嘔吐が止まらない最重度例では、一時的に絶食することもあります。しかし軽度~中等度の膵炎であれば絶食させないほうが回復が早いとも言われます。いずれにせよ与える食事は低脂肪かつ消化しやすい療法食を用い、1日のご飯を3~4回以上に小分けして少量ずつ与えるのが基本です。
副腎皮質ステロイドの使用
膵炎治療にステロイド?と思うかもしれませんが、最近では急性膵炎にステロイドが有効であったとの報告もあります。ステロイドの持つ強力な抗炎症作用で膵炎による症状やCRPの改善が認められたケースがあるのです。ただしステロイドを長期連用すると血栓形成の副作用リスクが上がるため、あくまで慎重に短期間の使用に留める必要があります。
新薬ブレンダZ(フザプラジブナトリウム水和物)
最近登場した膵炎治療薬にフザプラジブ(商品名ブレンダZ)があります。炎症性サイトカインの作用を阻害して白血球の異常な活性化を抑えることで、膵臓の炎症を鎮める効果があります。犬の急性膵炎に対して使える新しい治療薬で、副作用もほとんどなく安全に使用できるとされています(※ただし妊娠中・授乳中や3か月齢未満の子犬では安全性が確立していません)。ブレンダZはもともと急性膵炎専用薬でしたが、最近では膵炎以外のさまざまな急性炎症疾患でも有効性が報告されつつあります。
治療期間はどれくらい?
急性膵炎の場合、2~4日間程度の入院で集中的に治療を行うケースが多いです。退院後も自宅で低脂肪食への切り替えや必要な内服薬の投与を続け、完治まで1〜2週間ほどかけて様子を見るのが一般的です。もし治療を行わず放置するとショック状態に陥り数日で命を落とすこともあります。また急性膵炎を繰り返すと膵臓の組織が破壊され、不可逆的な慢性膵炎へ移行してしまうこともあります。慢性化すると完全に元通り治すことは困難になるため、やはり早期発見・早期治療が肝心です。
獣医師おすすめの低脂肪ドッグフード
「膵臓に良い低脂肪のフードがなかなか見つからない」「市販の低脂肪フードをあげているのに再発してしまう」「療法食を与えているが食いつきが悪い」——膵炎の食事管理について、このようなお悩みを抱える飼い主さんも多いのではないでしょうか。
質の良い低脂肪ドッグフードに出会えれば、愛犬の膵炎の改善はもちろん、食いつきが良く満足してくれるので余計なおやつを与えずに済み、さらに継続することで膵炎になりにくい体質へ体調を整えることも期待できます。つまり膵炎の再発防止にも繋がるのです。
では、どのようなフードを選べばそんな理想を実現できるのでしょうか?大切なのは次のポイントを満たすフードを選ぶことです。
- 膵臓に負担をかけない十分な低脂肪設計であること(脂質含有量が少ない)
- 膵炎になりにくい体質へ改善する成分を含むこと(消化吸収を助ける素材や抗炎症作用のある栄養など)
- 嗜好性が高く食いつきが良いこと(いくら療法食でも食べてくれなければ始まりません)
以上の条件を踏まえ、獣医師の視点から膵炎の愛犬におすすめできる低脂肪フード3選をご紹介します。いずれも低脂肪で消化に良いだけでなく、プラスアルファのメリットがある優秀なドッグフードです。
🐕 膵炎ケア用低脂肪ドッグフード おすすめ早見表
| 順位 | 商品名 (ブランド) | フードタイプ | 脂質含有量 | 主原料・特徴成分 | 価格帯 (目安) | 購入先 | 最大の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和漢みらいのドッグフード 【特別療法食(膵臓用)】 (犬心) | 特別療法食 | 超低脂肪 | 鹿肉、和漢素材89種類 マクロビ発酵素材 オメガ3脂肪酸 | 高級 | 公式サイト 一部動物病院 通販サイト | 和漢による体質改善 無添加・ヒューマングレード |
| 2位 | ロイヤルカナン 消化器サポート(低脂肪) | 獣医師専用 療法食 | 低脂肪 | 高消化性タンパク プレバイオティクス 抗酸化成分 | 中級 | 動物病院 Amazon・楽天 ペット薬局 | 世界的信頼・豊富な実績 科学的エビデンス |
| 3位 | ナチュラルハーベスト レジーム | 体重管理用 一般フード | 5%以上 | 乾燥チキン、大麦 全粒米 高繊維・低炭水化物 | リーズナブル | ペットショップ 通販サイト 全国で入手可能 | 手軽さ・コスパ良好 嗜好性が高い |
🎯 適用シーン別おすすめ度
| 使用シーン | 和漢みらい | ロイヤルカナン | ナチュラルハーベスト |
|---|---|---|---|
| 急性膵炎の回復期 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| 慢性膵炎の長期管理 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| 療法食を嫌がる犬 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 肥満併発ケース | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 予防・体質改善 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
💰 コスト比較(月額目安)
| 体重 | 和漢みらい | ロイヤルカナン | ナチュラルハーベスト |
|---|---|---|---|
| 小型犬(5kg) | 約8,000-10,000円 | 約4,000-6,000円 | 約3,000-4,000円 |
| 中型犬(15kg) | 約18,000-22,000円 | 約8,000-12,000円 | 約6,000-8,000円 |
| 大型犬(30kg) | 約30,000-35,000円 | 約15,000-20,000円 | 約10,000-13,000円 |
🔍 愛犬の状況別フード選択ガイド
🚨 急性膵炎からの回復期
おすすめ: ロイヤルカナン → 和漢みらい
- まずは獣医師推奨の実績豊富なロイヤルカナンで安定
- 体調が戻ったら体質改善を狙って和漢みらいへ移行
🔄 慢性膵炎の長期管理
おすすめ: 和漢みらい or ロイヤルカナン
- 和漢みらい:体質改善と免疫力向上を重視
- ロイヤルカナン:安定した栄養管理を重視
😤 療法食の食いつきが悪い
おすすめ: ナチュラルハーベスト → 和漢みらい
- まずは嗜好性の高いナチュラルハーベストで食事習慣を安定
- 慣れたら鹿肉で美味しい和漢みらいにチャレンジ
1. 和漢みらいのドッグフード【特別療法食(膵臓用)】(犬心)
特徴: 漢方生薬など89種類もの和漢素材を配合した国産の特別療法食です。主原料には高タンパクながら低脂肪の良質な鹿肉を使用し、さらに腸内環境に配慮したマクロビ発酵素材や、抗炎症作用が期待できるオメガ3脂肪酸、抗酸化成分であるファイトケミカルも豊富に含まれています。添加物は一切不使用で、素材にとことんこだわったヒューマングレードのフードです。
おすすめ理由: 膵炎に配慮して脂肪分を抑えつつ、和漢の力で体質改善をサポートしてくれる点が最大の魅力です。膵臓そのもののケアだけでなく、漢方の作用で免疫力向上や肝臓・腎臓の保護、胃腸の調子を整える効果も期待できます。また鹿肉メインで嗜好性が高く食いつきが良いため、療法食にありがちな「食べてくれない」という心配も少ないでしょう。実際に「飽きずに完食してくれる」「血液検査の数値が悪化せず安定した」などの飼い主さんの喜びの声も多いようです。
適しているケース: 獣医師から低脂肪食を指示された犬全般に適しますが、特に膵炎を繰り返している子や高齢で他の臓器ケアもしたい子に向いています。合成添加物に敏感な犬や、漢方を取り入れたい飼い主さんにも良いでしょう。
購入先情報: 公式サイトで購入できます(一部、動物病院や通販サイトでも取り扱いあり)。初回限定のお試しセットもあるのでまずは試してみるのがおすすめです。
2. ロイヤルカナン 消化器サポート(低脂肪)
特徴: 世界的に信頼の高いロイヤルカナン社の獣医師専用療法食です。脂質を抑え消化吸収に配慮した処方で、膵炎や高脂血症の犬のために設計されています。可溶性・不溶性両方の食物繊維をバランスよく含み、腸内環境を整えつつ便の質にも配慮。さらに消化吸収をサポートする高消化性タンパクやプレバイオティクス、抗酸化成分なども配合されています。
おすすめ理由: 急性膵炎からの回復期や慢性膵炎の管理食として世界中の動物病院で採用実績が豊富なフードです。科学的エビデンスに基づいて作られており、栄養バランスも総合栄養食として優秀です。低脂肪でありながら必要なカロリーや栄養素をしっかり摂取でき、体力の低下した犬の栄養補給にも適しています。食いつきも比較的良好で、小粒タイプもあるため小型犬でも食べやすいでしょう。
適しているケース: 膵炎の治療中・治療後の犬全般にまず第一選択となる療法食です。急性膵炎で退院後の食事に迷ったときや、慢性膵炎で長期にわたり食事療法が必要なときに特に向いています。また、高脂血症や胆泥症など脂質管理が必要な子にも利用されます。
購入先情報: 基本的には動物病院で処方されるフードですが、病院によっては取り寄せになる場合もあります。インターネットのペット薬局やAmazon、楽天市場などでも購入可能です(購入の際は獣医師の指示に従いましょう)。
3. ナチュラルハーベスト レジーム(Natural Harvest Regime)
特徴: 日本のプレミアムフードブランド「ナチュラルハーベスト」の体重管理用フードです。粗脂肪5%以上と一般フードの中では非常に低脂肪で、高繊維・低炭水化物の設計が特徴です。主原料は良質な乾燥チキンと大麦・全粒米で、減量をサポートするために高タンパク・低カロリーに調整されています。人工添加物や着色料は不使用で、自然由来の原料にこだわっています。
おすすめ理由: 元々は肥満犬のダイエット用フードですが、その低脂肪ぶりから膵炎経験犬の維持食としても適しています。総合栄養食なので長期の主食として安心ですし、何より嗜好性が高めで日頃療法食を嫌がる子にも試しやすい点がメリットです。粒のサイズ展開もあり、小型犬には「スモール」、大型犬には「ラージ」と愛犬に合わせて選べます。一般フード扱いのため入手しやすく価格も手頃です。
適しているケース: 膵炎の寛解後に体重管理も兼ねて使いたい場合や、療法食だと食べない犬への代替として適しています。また、まだ膵炎にはなっていないもののシニア期で肥満傾向があり予防したいケースなどでも、普段のご飯をこのフードに変えて脂肪摂取量を抑えるといった使い方ができます。
購入先情報: ペットショップやオンラインストア(Amazon、楽天など)で購入できます。動物病院専売ではないため通販で手軽に入手可能です。
膵炎は再発しやすい?慢性化に注意
膵炎は一度発症すると再発しやすい病気と言われます。急性膵炎を起こすと膵臓に炎症の傷跡(線維化による瘢痕組織)が残りやすく、これが膵臓の正常な機能を妨げて将来の膵炎再発の引き金になります。また繰り返し急性膵炎を起こすうちに前述の慢性膵炎へ移行するリスクも高まります。
慢性膵炎になると、膵臓が十分な消化酵素を分泌できなくなる膵外分泌不全(EPI)という状態を招くことがあります。消化酵素の不足により、食べ物をうまく消化吸収できず脂肪便(脂肪分を消化できずに白っぽくベタついた便)が大量に出たり、下痢がちになります。その結果、体重減少や栄養失調を引き起こしてしまいます。
※膵外分泌不全について詳しく知りたい方は、当サイト内の別記事『犬の慢性膵炎は治る?寿命・主な6つの症状・治療法や食事(低脂肪食)を獣医師が徹底解説』も参考にしてください。
膵炎の予防策
膵炎を完全に防ぐことは難しい場合もありますが、日頃の生活で次のような点に気を付けると膵炎の予防・再発防止に役立ちます。
体重管理を徹底する
まず重要なのは適正体重を維持することです。肥満との関連が深いとされる膵炎ですので、もし愛犬が太り気味と言われたら獣医師と相談しながら無理のないダイエット計画を立てましょう。適正体重にある犬でも、中高齢になれば基礎代謝が落ちて太りやすくなりますので、定期的に体重を測って増えすぎないよう管理します。食事量の調節はもちろんですが、毎日の適度な運動も大切です。
散歩が好きな子なら距離や時間を少し延ばしてみたり、運動嫌いな子でもおうちの中でボール遊びなど興味を引く遊びをして体を動かしましょう。飼い主さんも一緒に楽しめる方法で継続するのがコツです。また、足腰が弱って長い運動は難しい高齢犬には、関節に負担をかけない範囲で室内リハビリ運動をしたり、栄養面では関節ケアサプリや代謝を助けるサプリメントを利用するのも良いでしょう。
食事内容の見直し(低脂肪食)
膵炎の予防・再発防止には日常の食事管理も欠かせません。具体的には以下の点を心がけましょう。
- 高脂肪の食事を避ける: 肉の脂身やバターたっぷりの洋菓子など、人間用の脂っこい食べ物は厳禁です。市販フードでも粗脂肪が高めのものは控え、低脂肪フードや療法食を選びましょう。
- おやつの与えすぎに注意: 膵炎後は特におやつも低脂肪のものに限定し、量も控えめにします。犬用でもチーズやサラミ系のおやつは脂質が高いので避け、与えるなら茹でた野菜や**果物(無糖ヨーグルトを少量添える程度)**などが比較的無難です。何をどれくらい与えるか、必ず担当獣医師と相談の上で判断してください。
- 手作り食の場合: 必ず脂肪分の少ない食材を選びます。鶏ささみ・鳥の胸肉(皮なし)・白身魚・豆腐・卵白などが使いやすいでしょう。野菜やイモ類も上手に取り入れて栄養バランスを補いますが、後述のレシピ例を参考にしつつ長期連用は栄養の偏りに注意してください。
ヨーグルトはあげてもいい?
膵炎の子にヨーグルトを与えるなら、無糖かつ無脂肪のプレーンヨーグルトに限り、ごく少量を与える程度にしましょう。加糖タイプや脂肪分の多い濃厚ヨーグルトは避けてください(高脂肪の乳製品は膵臓への負担が大きいです)。
膵炎の犬向け手作り食レシピ(ささみとおいものごはん)
療法食を食べてくれなかったり、アレルギー等で与えられる市販フードが限られる場合、手作り食が選択肢になることもあります。ここでは膵炎の際によく紹介される**「ささみとイモ類」を使った超低脂肪食**のレシピをご紹介します。
- 療法食を嫌がって全く食べない
- 対応する療法食に使われている原料にアレルギーがある
- もともと好き嫌いが激しく、市販フードだと食が細い
といった場合、獣医師の許可のもと短期間だけ手作りの食事で栄養を補うのも一つの方法です。ただし完璧に栄養バランスを整えるのは難しいため、あくまで一時的な対応とし、長期の場合はサプリメントで栄養補填するなど工夫が必要です。
ささみとイモのごはんとは?
膵炎時の手作り療法食として昔から知られるメニューに「ささみとおいものごはん」があります。鶏のささみ肉とサツマイモ(またはジャガイモ)を組み合わせたシンプルな食事で、ULF(Ultra Low Fat)食と呼ばれる超低脂肪食の一種です。鶏ささみは肉類の中でも特に脂質が少なくタンパク質が豊富なため、膵炎を含む消化器トラブルの際に最適なタンパク源です。またイモ類も消化が良くビタミン類が補給できるため組み合わせに適しています。
参考までに、鶏肉の部位ごとの栄養価を一覧にすると以下のようになります(100g中の含有量)。
| 食材(可食部100gあたり) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | カロリー(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 鶏ささみ | 23.9 | 0.8 | 0 | 105 |
| 鶏むね肉(皮なし) | 24.4 | 1.9 | 0 | 113 |
| 鶏むね肉(皮あり) | 21.3 | 5.9 | 0 | 150 |
| 鶏レバー | 18.9 | 3.1 | 0.6 | 111 |
| 鶏もも肉(皮なし) | 19.0 | 5.0 | 0 | 125 |
| 鶏もも肉(皮あり) | 16.6 | 14.2 | 0 | 204 |
※文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」より抜粋。一部データは近似値。
ご覧のように、ささみ(脂質0.8g)や皮なし胸肉(1.9g)は極めて低脂肪であるのに対し、皮付きの部位では脂質が大幅に増えることがわかります。膵炎時の手作りごはんでは皮や余分な脂は必ず除去し、できるだけ脂肪分をカットしましょう。
超低脂肪のささみ+イモ食は、膵炎以外にも犬のタンパク漏出性腸症(リンパ管拡張症)や消化器型リンパ腫など、脂肪制限が必要な疾患の食事として応用されることがあります。それほどまでに「低脂肪」であることがこのメニューの利点なのです。
さらにイモ類(サツマイモやジャガイモ)は炭水化物源として血糖値の上昇が比較的ゆるやかで、膵炎時に二次的に負担がかかりやすい**膵島(インスリン分泌)**にも優しい食材です。もし膵炎と同時に腎臓病も抱えている場合は、カリウム含量の少ないジャガイモを使うなど素材選びの工夫もできます(サツマイモはカリウムが多めなので腎臓の数値が高い子には要注意)。
サツマイモの栄養メリット
ここで、組み合わせるサツマイモの栄養面でのメリットも押さえておきましょう。サツマイモには様々なビタミン・ミネラルや食物繊維が含まれ、犬の体に嬉しい効果をもたらします。
- 食物繊維: サツマイモは食物繊維が豊富です。腸内細菌のエサとなって腸内環境を整えたり、有害物質(アンモニアなど)の発生を抑えて血液を綺麗にする働きがあります。また消化を助ける作用もあるため、膵炎で便がゆるくなりがちな時の整腸に役立ちます。さらに食物繊維は満腹感を維持してくれるので、肥満気味の子のダイエットにも効果的です。
- 抗酸化物質: サツマイモには抗酸化物質も含まれています。特に紫色のサツマイモにはポリフェノールの一種アントシアニンが多く含まれ、橙色のサツマイモにはβカロテンが豊富です。抗酸化物質は体内で発生するフリーラジカル(細胞を傷つける物質)を除去し、ストレスや病気によるダメージから体を守る働きがあります。
- ビタミン類: サツマイモは多様なビタミンを含みます。例えばビタミンCは免疫力維持に役立ち、高齢犬の認知機能低下を緩和する報告もあります。サツマイモ由来のビタミンCは熱にも比較的強く、加熱調理しても損失が少ないとされています。またビタミンA(目や皮膚、粘膜の健康維持に不可欠)、ビタミンB群(B1は炭水化物のエネルギー化、B6はアミノ酸代謝に関与)、ビタミンE(抗酸化作用)なども含まれています。
- ミネラル類: カルシウムやカリウム、鉄分などのミネラルも適度に含んでおり、体の機能維持に寄与します。特にカリウムは余分なナトリウムを排出してむくみ予防にも役立つミネラルですが、腎臓が悪い子には多すぎると良くないため注意です。
サツマイモは皮ごと与えてもいい?
サツマイモは必ず皮をむき、十分に加熱調理して与えましょう。皮の部分は犬にとって消化しにくく、栄養価もあまりありません。それどころか皮にはシュウ酸という尿路結石の原因物質が含まれるため、特に膵炎で体調が落ちている時期には避けたほうが無難です。未調理の生芋や皮付きのまま与えると消化不良を起こす恐れもあります。
手作り超低脂肪食を与える量の計算方法
手作り食で気をつけたいのが適切な給餌量です。市販フードのように給与量の目安表示がありませんので、まず愛犬に必要な1日のエネルギー量を計算し、それに見合った食材の量を決めます。以下の手順で簡単に算出できます。
- **安静時エネルギー要求量(RER)を計算する
ワンちゃんの体重から、まず安静にしている状態で必要な基礎カロリーを求めます。計算式はシンプルで、RER = 70 ×(体重kg)^0.75(体重の0.75乗に70を掛ける)
という式が知られています。ただ計算が少し面倒なので、近似式として「70 + 体重(kg)×30」**でも概算可能です。 - 1日に必要な総エネルギー量を算出する
次に、その子の活動量などを考慮した1日の必要カロリー(DER:1日エネルギー要求量)を求めます。一般的な成犬の維持ならRERの1.4~1.6倍程度が目安なので、ここでは1.5倍とします。
つまり、1日必要エネルギー量 ≈ RER × 1.5 - 各食材の分量を決める
算出した1日必要エネルギー量に対し、2/3をタンパク源(ささみ)から、1/3を炭水化物源(イモ類や白米など)から摂るよう配分します。
ささみは茹でたもの100gあたり約110kcal、ジャガイモ(皮なし茹で)100gで約80kcal、サツマイモ(皮なし茹で)100gで約130kcalが目安です。これらを使ってグラム換算しましょう。
≪計算例:体重3kgのケース≫
- RERを計算
RER = 70 + 3(kg) × 30 = 70 + 90 = 160 kcal - 1日必要エネルギー量を計算
160 × 1.5 = 240 kcal - 各食材から摂るカロリー配分を決定
- ささみ由来 = 240 × (2/3) = 160 kcal
- イモ由来 = 240 × (1/3) = 80 kcal
つまり体重3kgの犬なら、1日にささみ約145gとジャガイモ100gを食べれば240kcalを賄える計算です。
各ワンちゃんの体重によってこの量は異なりますので、上記式を参考に必要カロリーと分量を割り出してください。肥満傾向なら係数1.3倍程度にする、逆に痩せ気味で増量したいなら1.6倍にする、など微調整は獣医師に相談しながら決めると安心です。
《レシピ》ささみとおいもの超低脂肪ごはん
計算で必要量がわかったら、あとは実際に調理するだけです。
材料(1日分)
- 鶏ささみ肉:適量(上記計算例では約145g)
- サツマイモまたはジャガイモ:適量(計算例では100g)
- 水:適量
作り方:
- サツマイモ(またはジャガイモ)は皮を厚めに剥き、柔らかくなるまで茹でます。フォークでスッと刺さるくらいになればOKです。
- 鶏ささみも沸騰したお湯で茹で、中までしっかり火を通します。茹で汁は捨てずに取っておきます。
- 茹で上がったささみを細かくほぐし、茹でたイモと一緒に器に盛り付けます。水分摂取量を増やしたければ、ささみの茹で汁を少しかけてあげても良いでしょう。
以上です。とてもシンプルですが、タンパク質と炭水化物だけで構成された超低脂肪食の完成です。サツマイモの代わりにジャガイモを使ったり、ささみの代わりに脂肪の少ない胸肉(皮なし)で代用しても構いません。
<small>※この食事はあくまで緊急避難的な療法食であり、長期に続けると栄養が偏ります。もし1週間以上にわたり手作りせざるを得ない場合は、カルシウムやビタミンD、亜鉛など不足しがちな栄養素を補える総合栄養サプリメントを獣医師と相談の上で追加してください。</small>
鶏肉アレルギーの場合は?
中には鶏肉にアレルギーがあって使えない犬もいます。その場合は、馬肉や鹿肉といった他の低脂肪高タンパクな肉で代用できます。ただし部位によっては脂質が多いこともあるため、極力赤身の部分を選び脂肪は取り除いて与えましょう。魚であれば**白身魚(タラ、ヒラメなど)**も低脂肪で良いタンパク源になります。
また覚えておいていただきたいのは、犬は人よりも肉食寄りの雑食だという点です。植物性の繊維質の消化はあまり得意ではありません。そのため手作り食では、野菜類はなるべく細かく刻んで柔らかく煮込むなど消化を助ける工夫が必要です。一方で動物性タンパクは比較的消化しやすいので、膵炎の療法食でもお肉をメインに据えてOKです(もちろん脂肪を落とした部位に限ります)。
なお、膵炎の犬すべてが脂質異常症になるわけではありません。中には脂質代謝は正常で膵炎を発症した子もいます。こうした場合、極端に脂肪ゼロに近い食事だと逆にカロリー不足になるケースもありますので、担当獣医師の指導のもと適度な脂肪も摂取すべきという考え方もあります。手作りにせよ市販フードにせよ、愛犬の状態に合わせて栄養バランスを調整することが大切です。
膵炎の致死率・予後・寿命への影響
気になる膵炎の予後ですが、重症度によって大きく異なります。統計では、犬の急性膵炎の**致死率は27~58%**と報告されています(程度の差はありますが、実はこの数値、人間よりも高いのです)。特に多臓器不全や膵膿瘍、腹膜炎などの合併症を起こしている場合、残念ながら死亡率はさらに上がってしまいます。
もちろん全ての膵炎がこれほど致命的というわけではありません。軽症であれば適切な治療により数日で回復するケースも多くあります。早期発見・早期治療ができれば、死亡率を大きく下げ良好な予後が期待できます。逆に「様子を見よう」と受診を遅らせてしまうと、みるみる容態が悪化して手遅れになる危険があるため注意が必要です。
一度膵炎から回復した後も、前述の通り再発リスクがありますので寿命を全うするまで油断は禁物です。慢性膵炎へ移行した場合には生涯にわたり食事管理が欠かせなくなります。
家族(飼い主)だからこそできること
可愛い愛犬にはついつい甘やかしてお裾分けをしたくなるものですよね。「ほんの一口だから…」「欲しがるから可哀想で…」と、人の食べ物や脂っこいおやつを与えてしまう飼い主さんも少なくありません。そのお気持ちは痛いほど分かります。しかし、膵炎を経験した子にとってそれは命取りになりかねない行為です。
絶対にダメ!とまでは言いませんが、与えるならごく少量を“たまに”に留めましょう。特に揚げ物や焼肉の脂身、生クリームたっぷりのケーキなど、人間には美味しくても犬には高脂肪なものは厳禁です。また、人は平気でも犬に有害な食べ物(玉ねぎ、ネギ類、チョコレート、キシリトールなど)は論外です。
後になって「もっと気をつけていれば…」と後悔しても時間は戻りません。愛犬を膵炎から守るため、日常生活に潜むリスク要因を今一度チェックしましょう。例えば次のようなシーンに注意です。
- 庭や散歩中に農薬・除草剤のかかった草を口にしないようにする
- 獣医師の指示なくステロイド等の薬剤を自己判断で与えない
- 散歩中の拾い食いをさせないよう口輪やリードでコントロールする
- おもちゃや靴下などの異物誤飲に気をつける(腸閉塞から膵炎になるケースも)
- テーブルやキッチンに犬が届く場所に食べ物を置きっぱなしにしない(盗み食い防止)
一瞬の油断が取り返しのつかない結果を招くこともあります。「うちの子は大丈夫」と思わず、日頃から危険を遠ざけてあげるのも家族である飼い主さんの大切な役目です。
犬の膵炎まとめ
長くなりましたが、最後に本記事のポイントをまとめます。
- 膵炎とは、膵臓という消化器官で消化酵素が暴走して起こる激しい炎症です。
- 膵炎の原因は多岐にわたりますが、実際には**原因不明(特発性)**が大半を占めます。
- 膵炎の初期症状は嘔吐や下痢、腹痛など。末期には低体温、腹膜炎、血栓症、黄疸などショック症状が現れ命に関わります。
- 急性膵炎の死亡率は**約27~58%**と高く、特に重症例では多臓器不全による致死率が上昇します。
- 膵炎の治療は点滴、制吐剤、鎮痛剤、制酸薬、栄養管理などを組み合わせて行います。近年は早期の経口栄養と新薬ブレンダZの使用が注目されています。
- 膵炎では低脂肪食への切り替えが不可欠。特に鶏ささみ+イモ類の超低脂肪手作り食は一時的な療法食として有名です。
- 逆に脂肪分の高い食事は膵臓へ大きな負担をかけるため厳禁。与えるなら無脂肪無糖のヨーグルト程度に留めましょう。
- 手作りフードは新鮮で嗜好性も良い反面、栄養素が不足しがちなので長期連用は避け、続ける場合はビタミンDやカルシウムを含むサプリメントを併用することが重要です。
- 膵炎は放置すると命に係わる非常に恐ろしい病気です。嘔吐などの初期症状が認められたら様子を見ずすぐ動物病院へ受診することが大切です。
愛犬が膵炎になってしまうと飼い主として本当に心配で不安になるものです。しかし早めに気付き適切に対処すれば、元気な姿を取り戻せる可能性は十分にあります。「なんだか様子がおかしい」と感じたら早めに動物病院へ——この心掛けが愛犬の命を救うことに繋がります。愛犬とのかけがえのない日々を守るため、膵炎に関する正しい知識と対策をぜひ活用してくださいね。
